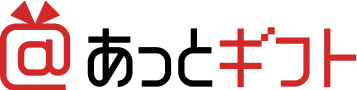アンケートの回答率を上げるコツ~答えたくなる仕掛けとは~
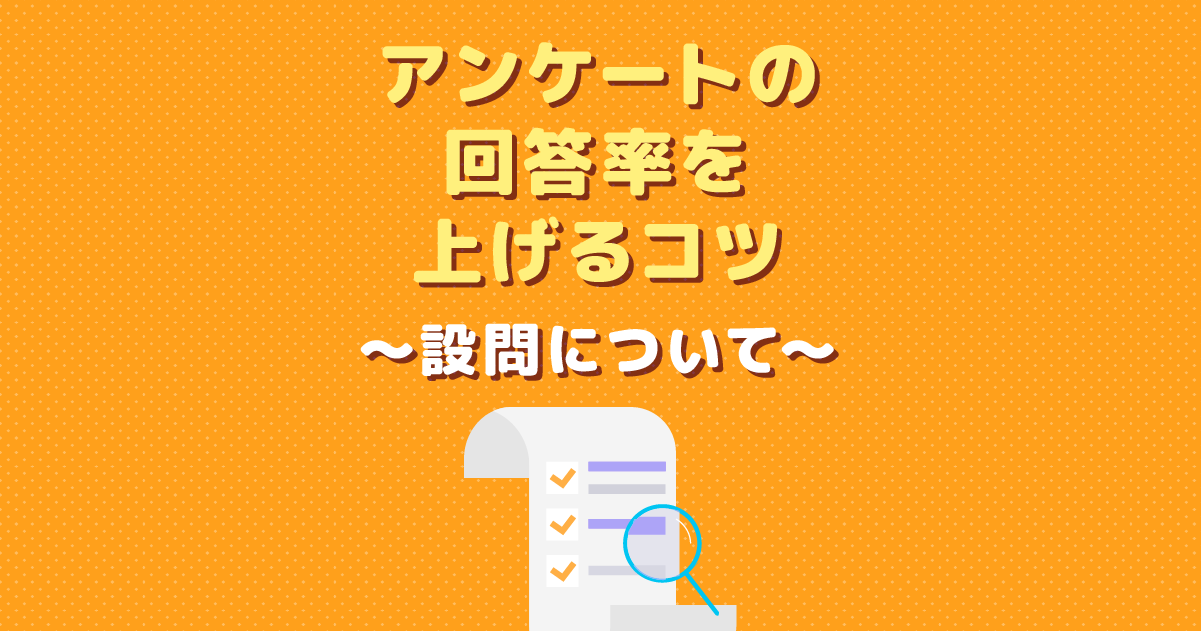
公開日: 2023年06月30日 更新日: 2025年07月03日
目次
アンケートの「回収率」「回答率」とは?
アンケートに関連した記事でよく見かけるワードに「回収率」「回答率」があります。
回収率・回答率ともに意味は同じで、配信・配布したアンケートに対して回答した人の割合のことです。例えば、アンケートを1000人に配信・配布し、600人が回答すると、回収率(回答率)は60%となります。
アンケートの回答率を上げるのは難しい?
マーケティング調査の一環として多くの企業がアンケートを実施しています。
自社の商品やサービスに対するユーザーの声を収集でき、得られた回答をもとに商品・サービスの魅力や利用するメリットなどを数字でアピールできるためです。
そのような状況の中、自社のアンケートに興味を持っていただき、なおかつ有効な回答を集めることは簡単ではありません。
1つの目安として、内閣府が実施している「青少年のインターネット利用環境実態調査」を見てみましょう。
令和4年度の回収率は、青少年(満10~17歳)は64.6%、その保護者は65.5%でした。
いくつかの回収方法がとられ、「訪問回収」は青少年31.6%、保護者51.0%。「Web回収」は青少年9.0%、保護者9.8%。「郵送回収」は青少年4.4%、保護者4.7%という結果でした。
令和4年度 青少年のインターネット利用環境実態調査
特に、「Web回収」の結果からわかるように、インターネット上で実施するアンケートの回収率を上げるのは難しいことがわかります。
しかし、回答しやすい工夫をすることで回収率を上げることが可能です。

アンケートの回答率が上がらない理由
ユーザーがアンケートキャンペーンについてどのように考えているかまとめました。
1.「忙しくて回答する時間がない」「回答に時間がかかりそうだった」
回答率が上がらない際に、もっとも多く挙げられる理由です。
興味はあっても、すべて回答するまでにどれくらい時間がかかるのかわからない、回答してみたものの設問数が多く途中離脱した、という経験は誰しもあるのではないでしょうか。
また、仕事や家事で忙しい時間帯にアンケートが届き、後で回答しようとそのまま忘れられてしまうこともあります。
2.「取得した個人情報を何に使うのか不安だった」
回答者が安心して率直な意見を述べられるよう、氏名や所在地などを記入しない匿名アンケートを実施するケースがスタンダードです。取得する個人情報は回答者のメールアドレスだけで、その安心感から、昨今、アンケート回答のハードルはぐんと下がりました。
しかし、アンケート回答後にセールスメールが届くかもしれないという懸念から、アンケートへの回答を思いとどまることも少なくありません。
3.「任意なので自分が答えなくてもいいと思った」
アンケートへの回答は任意です。自社の商品やサービスの愛用者なら快く協力していただけますが、そのような人たち以外は「誰かが回答する」から「自分が回答する(したい)」へ意識がシフトするようなきっかけがないと、多くの回答を集めるのは難しいでしょう。
アンケートの回答率を上げるコツ・答えたくなる仕掛け
回答率を上げるには、アンケートが届いたときに「忙しいからやめよう」「時間がかかりそうだから後にしよう」と思われない工夫が大切です。
ここでは、そのように思われない設問づくりなどのポイントを説明します。
1.回答者の負担が最小限となる設問にする
回答者の負担を最小限にするには、以下に配慮して設問をつくりましょう。

設問数を少なくする
設問数を少なくするために、まずはアンケートの目的を明確にし、テーマは可能であれば1つ、多くても2つに絞りましょう。設問数の目安は20問前後。回答にかかる時間は10分以内が理想です。
設問文は端的でわかりやすく
設問文は、1問につき70字程度、7秒以内に読める長さが理想です。ただし、文章を短くできるからといって名称の略語は使わないこと。さらに、専門用語、業界用語も同様です。一般的に伝わりにくい場合があります。
選択式で回答を選べるようにする
アンケートは、回答を複数から選べる選択式を中心に構成しましょう。
選択式にはいくつか種類があります。
- スケール
「どのくらい満足しているか」などを段階で評価してもらう設問形式です。「満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満・不満」の5段階が一般的ですが、選択肢が多いほど回答が分散するので細かくデータを見ることができます。
ただし「どちらともいえない」に集中しやすく、意図しない回答をされる場合があります。
- マトリックス
5段階評価で行なう点はスケールと同じですが、マトリックスは1問につき複数の項目を設定できます。「価格、使いやすさ、機能性、品質、入手のしやすさ」などの項目を設けることで、商品やサービスの評価を総合的に見ることができます。
しかし、総設問数が増えがちになり、回答者の負担が大きくなる場合があります。
- ラジオボタン
用意した選択肢から1つだけ選んでもらうタイプです。選択肢が少ない設問に適しています。回答者の考えや嗜好など、パーソナルな情報を把握できます。
- チェックボタン
用意した選択肢から複数の回答を選べるタイプです。回答者の環境・需要・要望を把握することができます。
選択式のほか、記述式の「テキストボックス」も回答任意で設置します。選択式で答えていく中で商品やサービスについての意見や感想を思い出す場合があります。潜在ニーズにつながる貴重な情報なので、自由記入欄は必ず設けましょう。
2.アンケートの回答にかかる目安時間と設問数を記載する
アンケートに興味を持ち、回答しはじめたものの、いつ終わるのかが見えず途中離脱してしまう状況を避けるためにも、回答時間や設問数を記載しましょう。
「回答にかかる時間は約10分です(全15問)」と明記しておけば、回答者の心づもりができます。
3.アンケートを送る曜日や時間帯に配慮する
仕事や家事で忙しいタイミングにアンケートが送られてきても、後まわしにされ、そのまま忘れられてしまうことがあります。これもアンケートの回答率が上がらない原因の一つです。
では、どのようなタイミングだと目にとまり、回答してもらいやすいのでしょうか。
ターゲットとする層の職業にもよりますが、例えば、土曜・日曜が休みなら、その前日である金曜の夕方以降が、比較的落ち着いている時間帯であると推測できます。
ターゲットとする層にとって、ゆとりをもってアンケートに答えられるであろう曜日や時間帯に配慮し、配信のタイミングを計ることも大切です。
アンケートの回答率を上げるコツ・回答者への配慮
1.挨拶文でアンケートの目的と回答の活用法を説明する
アンケートの冒頭、挨拶文にて「どこの企業が」「なぜアンケートを実施するのか」を伝えましょう。可能ならば、「送っていただいた回答がどのように活かされるのか」も明記できると、回答者のモチベーションが上がります。
2.個人情報の取り扱い方針を明確にする
回答が送られてきた際に回答者のメールアドレスを取得します。得た個人情報の取り扱い方針を明確にすることも大切です。
注意すべきポイントは3つあります。
- 個人情報の利用目的を具体的に明記する
- 取得した個人情報は第三者に提供しない
- 責任者を定め、問い合わせ先を記載する
特に1つめの「個人情報の利用目的を具体的に明記する」が重要で、出来る限り目的を特定することで回答者の安心につながります。
記載内容が多い場合は、自社のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を記載したホームページへ誘導するのもいいでしょう。
3.回答者への感謝も込めて「謝礼」を送る
「誰かが回答する」から「自分が回答する(したい)」へ意識がシフトするようなきっかけとして、もっとも有効なのは「謝礼」です。なかでも「デジタルギフト」がおすすめです。
物品の場合、送付するために氏名や住所といった個人情報を追加で取得しなければなりませんが、デジタルギフトならば回答で得た回答者のメールアドレスへ送るだけです。
回答者にとっては企業に渡る個人情報が少なく安心で、企業にとっては郵送や在庫管理の手間やコストがかからないというメリットもあります。
また、デジタルギフトには、Amazonで使える「Amazon ギフトカード」や、実店舗やECサイトで利用できる「PayPayポイント」など、さまざまなバリエーションがあるため、年齢などを問わず喜ばれる謝礼を送ることができます。
アンケート回答の謝礼については『アンケート回答の謝礼相場について~喜ばれる謝礼も紹介~』にて詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。
アンケートの作成方法
アンケートには「Web」「紙」などを用いますが、どのような媒体であろうと、基本的な作成手順は以下のとおりです。
1.アンケートのテーマを決める
2.設問票の設計
設問内容・順番を決める
設問文を作成する
回答形式(スケール、ラジオボタンなど)を決める
選択肢を決める
3.設問文などの校正
※誤字脱字だけでなく、設問がわかりやすいか、誘導的ではないか、あいまいな問いかけになっていないかなどもチェックする
4.設問票の作成
Web:Webアンケートフォームに落とし込む
紙:印刷する
「Webアンケートフォーム」には、無料で使えるものから多彩な機能を備えた有料まであります。スピーディかつ低コストでアンケートを実施でき、回収した回答は即時にデータ化、集計・分析がしやすいメリットがあります。
選ぶポイントとしては
- 設定できる設問数
- セキュリティ対策
- 集計のしやすさ(自動集計やダウンロード機能)
を基準にするといいでしょう。
「あっとギフト」では、アンケートフォームの開発をはじめ、設問づくりから報告書作成までアンケートキャンペーンをワンストップでお請けしています。回答者へデジタルギフト(謝礼)の即時配布にも対応していますので、まずはご相談ください。
まとめ
アンケートの回収率を上げるには、直感で答えられる選択式をメインに設問をつくるのがポイントです。しかし、聞きたいことを羅列するのではなく、一人ひとりと面談するような気持ちで、丁寧に設問をつくり上げましょう。
どのような問いなら答えやすいか試行錯誤して出来上がった設問を、実際に自分に質問してみることをおすすめします。意外に回答が難しいと思うもの、回答が1つに偏りがちになるものなど、つくっているときには気づかなかった課題が見えてきます。
そのように心をこめて丁寧につくり上げたアンケートには、回答者も積極的に意見や感想を伝えてくれるはずです。