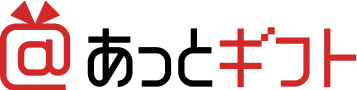【挨拶状の文例付き】 法人・取引先へのお歳暮マナーと冬ギフト事情 ビジネスで差がつく贈り方

公開日: 2025年10月14日
年末のビジネスシーンを象徴する「お歳暮」は、取引先や顧客との関係を深める大切な冬ギフトの習慣です。しかし、その贈り物選びに頭を悩ませる担当者も多いのではないでしょうか。近年はカタログギフトが定番化する一方、デジタルギフトの活用も注目されています。本記事では、お歳暮の基本からビジネスならではのマナー、さらにデジタルギフトを活かした新しい贈り方まで、法人向けの冬ギフト事情について詳しく解説します。
目次
お中元のマナーと最新ギフト事情
年末のビジネスシーンにおいて、取引先や顧客への「お歳暮」は、感謝の気持ちを伝える重要な習慣です。近年では、従来の訪問・手渡しから配送が主流となり、贈る時期やマナー、品物選びにも変化が見られます。特に、相場やのしの書き方、挨拶状の文例など、ビジネスならではの配慮が求められる場面も多く、担当者にとっては悩みの種となりがちです。
また、ギフトの選定においても、部署単位で配りやすいお菓子や、年齢性別問わず喜ばれるお茶・コーヒー、選ぶ楽しみを提供するカタログギフトなどが定番ですが、最近では住所不要で受け取れる「デジタルギフト」が注目されています。利便性の高さから、年末の多忙な時期にもスマートに対応できる新しい選択肢として、導入を検討する企業が増えています。
こうした流れの中で、法人向けデジタルギフトサービス「あっとギフト」は、ギフトの手配から挨拶状の準備、受け取り状況の管理までを一括でサポート。贈る側の負担を軽減しつつ、受け取る側の満足度も高める仕組みが整っています。年末のご挨拶をよりスマートに、そして印象的にしたい企業様におすすめのサービスです。
資料ダウンロードお歳暮とは?
「今年もお世話になりました。」
そのひと言を形にするのがお歳暮という冬ギフトの文化です。取引先や顧客へのお歳暮は、単なる贈り物というだけでなく、ビジネスの信頼関係を示す大切な儀礼でもあります。
そもそも「お歳暮」とは、年の暮れにお世話になった相手へ感謝を伝えるために贈る物です。語源は「歳(とし)の暮れ」という意味で、元々は先祖への供物を年末に届ける習わしから発展しました。やがて江戸時代頃から、日頃お世話になった人々や取引先などに贈り物を渡す慣習へと広がり、現代のビジネスシーンにも受け継がれています。
一方、お中元もお歳暮と並ぶ代表的な季節の贈り物ですが、大きな違いは贈るタイミングと意味合いです。お中元は夏に贈り、上半期のお礼や無病息災を願う意味があります。これに対し、お歳暮は一年の締めくくりとして、特に「来年も変わらぬお付き合いを」という未来へのご挨拶を込める点がビジネスでは重要です。
ビジネスシーンにおけるお歳暮
ビジネスシーンにおけるお歳暮は、いまだ根強い慣習として引き継がれつつも、少しずつ様変わりしています。従来は直接訪問して手渡しするケースが多かったものの、近年は配送が主流です。
贈る時期はいつがベスト?
お歳暮の一般的な時期は12月初旬〜20日頃にかけてですが、ビジネスの現場では少し早めに贈るのが鉄則です。取引先や顧客には、相手企業が年末進行で忙しくなる前の12月上旬〜中旬に届くよう手配するのがおすすめです。もし贈りそびれてしまった場合は、松の内(1月7日頃)までは「お年賀」、それ以降から立春までは「寒中見舞い」として贈るのがマナーです。
気になる相場・予算
法人・取引先へのお歳暮の相場は、おおむね3,000円〜5,000円程度が一般的とされています。ただし重要な顧客や長年の取引先など、関係性によっては5,000円〜10,000円ほどの品物を選ぶケースもあります。あまりにも高額すぎると先方に負担を感じさせる恐れがあるため、相手との関係性や業界の慣習も踏まえつつ予算を決めましょう。
ビジネスにおけるお歳暮のマナーと注意点
取引先や顧客向けのお歳暮は、贈る品物だけでなく、贈る際のマナーや手続きにも細やかな気配りが求められます。以下のような基本的なマナーや注意すべきポイントは、しっかり押さえておきましょう。
のし・表書きは必須
ビジネスでのお歳暮には、のし紙を掛けるのが基本です。表書きには「御歳暮」や「お歳暮」と記載し、水引は紅白の蝶結びが一般的です。贈るのが遅くなる場合、1月7日頃までは「御年賀」、それ以降は「寒中御見舞」と記載しましょう。
法人の場合、表書きの下段には贈り主の会社名を入れますが、担当者の個人名を併記するかどうかは相手との関係性によります。「会社名+部署名」または「会社名+代表者名」で記載するケースもあります。
手渡しか配送か
従来は直接訪問して手渡しするのが正式とされてきました。しかし昨今では、先方の業務多忙や働き方改革などの影響もあり、配送を選ぶ企業が増えています。もし訪問して手渡しする場合は、事前にアポイントを取ることが必須です。突然の訪問は、かえって先方に迷惑をかける恐れがあるため避けましょう。また、贈り物は紙袋に入れたまま持参しますが、渡すときには袋から出して品物を相手に見せてからお渡しするのが礼儀とされています。
一方で配送を選ぶ場合でも、送り状や挨拶状を必ず同封する、もしくは別便で挨拶状を送るなどの点に気をつけましょう。送り状の宛名は、基本的に会社宛で問題ありません。ただし、特定の担当者や役員が日頃からお世話になっている場合には、「会社名+役職名+氏名」とすることで、より丁寧な印象を与えられます。
挨拶状の文例
取引先や顧客にお歳暮を贈る際は、挨拶状を添えるのがマナーです。以下のような例文を参考に、挨拶状を作成しましょう。
株式会社〇〇
営業部 部長 佐藤花子様
拝啓 師走の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年も株式会社〇〇様には多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
日頃の感謝の気持ちを込めまして、心ばかりの品をお届けいたしましたので、ご笑納いただけましたら幸いです。
来年も変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
まずは略儀ながら、書中をもちまして歳末のご挨拶を申し上げます。
敬具
令和〇〇年十二月
株式会社〇〇
営業部 田中太郎
避けた方がよい品物
ビジネスにおけるお歳暮では、以下の品は避けておきましょう。おすすめのギフトについては、後述の章でご紹介します。
- 現金や高額すぎる商品券(不正取引などを疑われるリスクがあるため)
- 刃物(「縁を切る」と連想されるため)
- ハンカチ(別れや涙を連想させるため)
- 香典返しで定番の品(海苔や緑茶など。地域によって異なる)
喪中・忌中の場合の対応
ビジネスシーンでは先方または自身が喪中でも、慣習的にお歳暮を贈ること自体は差し支えないとされています。ただし華美な贈り物は避け、シンプルな白い短冊に「御歳暮」の表書きをするなど配慮をするといいでしょう。ただし、忌中(四十九日以内)、また新年を祝う松の内(1月1日から1月7日)は避け、贈る時期をずらすのが無難です。
ビジネスシーンでのお歳暮におすすめの品物は?

お歳暮選びに頭を悩ませ、毎年同じ物を贈っているという企業も少なくないでしょう。「取引先の好みに合わないと失礼になるのでは」「他社と被ってしまうかも」など、法人ギフトには気をつかうポイントがたくさんあります。ここでは、ビジネスシーンで安心して贈ることができ、かつ相手の満足度も高い冬の贈り物をジャンル別に紹介します。
定番で安心感のある「お菓子」
ビジネス用途では、個包装された焼き菓子や和菓子が根強い人気です。部署単位で配りやすく、日持ちもするため、受け取った側の負担が少ないこともメリットです。たとえば、老舗のどら焼きやフィナンシェ、バウムクーヘンなどは、見た目も上品で「気が利いている」と好印象を持たれます。
幅広い層に喜ばれる「お茶・コーヒー」
年齢や性別を問わず贈りやすいのが、お茶やコーヒーのギフトです。急須で楽しむ高級煎茶や、ドリップバッグのスペシャルティコーヒーなど、品質にこだわったアイテムは贈答用として人気です。「寒中見舞い」や年始の挨拶と併せて贈るケースも多く、冬ギフトの定番になっています。
お酒好きな方には「ビール・お酒」
お酒好きの企業や役職者に好まれるのが、冬限定の地ビールセットや銘酒の詰め合わせです。ただし、アルコール類は苦手な方もいるので、相手の嗜好を把握している場合やこれまでの付き合いが深い場合におすすめです。年末年始に向けた特別感のあるギフトとして、印象に残る品物でもあります。
選ぶ楽しみを提供する「カタログギフト」
法人ギフトでポピュラーなのがカタログギフトです。予算に応じたコース選定がしやすく、食品・日用品・雑貨などから相手が好きなものを選べるため、「贈り物で迷ったらこれ」という安心感があります。最近ではデザインも洗練され、法人向けに特化した高級ラインも充実しています。
受け取りやすさで注目される「デジタルギフト」
近年、注目されているのがデジタルギフトです。受け取り側が住所を開示しなくても、メールアドレスだけで簡単に受け取れるのが最大のメリットです。実際に「配送先の登録が面倒」「相手の異動で住所が不明」など、従来のギフトでは起こりがちなトラブルを避けることができます。
また最近では、ビールギフトやグルメカード、選べるデジタルカタログなど選択肢も増えており、カタログギフトからの切り替えを検討する企業も増えつつあります。特に、年末年始の多忙な時期には、いつでもどこでも受け取れるデジタルギフトは、受け取る側の利便性も考慮したギフトとして好まれる傾向にあります。
ビジネスでのお歳暮には「あっとギフト」
年末のご挨拶として取引先や顧客に贈るお歳暮は、大切なビジネスマナーのひとつですが、ギフトの選定から手配、挨拶状の準備、配送の管理まで、多くの作業が発生し、総務や秘書担当者の負担となりがちです。そこでおすすめなのが、デジタルギフトを活用した法人向けギフト支援サービス「あっとギフト」です。手間を大幅に省きつつ、相手への印象をしっかりと残せる、新しいお歳暮のかたちです。
冬に喜ばれるギフトが充実
「あっとギフト」では、AmazonギフトカードやPayPayポイントなど定番のデジタルギフトカード以外にも、お取り寄せスイーツやフルーツなどのグルメカード、定番のお歳暮アイテムであるビールや飲料なども選べるデジタルカタログギフトなど、魅力的なギフトを豊富に取り揃えています。各商品の発行元との個別契約は不要で、スムーズにギフト手配が行えます。
選べるギフトで好みや職場事情にも配慮
取引先によっては、社内規定で受け取れる物品に制限がある場合もあります。そんなとき、「選べるギフト」形式なら、受け取る側が自分の希望に合った商品を選べたり、内容を贈る先の社内規定にあったものだけに制限したりと、不要なすれ違いを防ぎつつ満足度も向上します。贈る側も、細かい好みや規定を気にせず安心して贈ることができます。
ビジネスマナーも押さえた贈り方
お歳暮は感謝の気持ちを丁寧に伝える贈り物です。ギフトの内容はもちろん、贈り方そのものにも気を配りたいところです。あっとギフトなら、オリジナルの台紙やメッセージカードをつけることができ、きちんとした印象を保ったままデジタルギフトを届けられます。法人向けに最適化された設計だから、格式を重んじる企業にも安心です。
贈り先の受取り状況を機能してミスを防止
複数の取引先にお中元を贈る場合、「誰に、いつ、何を送ったか」 の管理は非常に重要です。あっとギフトでは、贈り先の送付状況を一元管理できるため、贈り漏れや重複を防ぐことが可能です。翌年以降の参考データとしても活用でき、社内報告資料の作成にも役立ちます。
面倒な手配はすべてお任せ
お歳暮のシーズンは、社内も慌ただしい時期。ギフトの手配から配送までを一括で代行してくれるあっとギフトなら、担当者の負担を大幅に軽減できます。特に多くの取引先を抱える企業にとっては、手間と時間の削減につながる非常に効率的な選択です。
お歳暮も“スマート”に贈る時代へ
年末のご挨拶であるお歳暮は、単なる贈り物ではなく、1年間の感謝と今後の関係性を築く大切なビジネス習慣です。しかし、現代の忙しいビジネスシーンでは、すべての工程を自社で対応するのは非効率なこともあります。
その点、あっとギフトのような法人向けデジタルギフトサービスを活用すれば、ギフト選定から送付、配布状況の管理までを効率化でき、相手への印象も損なうことなくスマートにお歳暮を贈ることができます。
形式だけにとらわれず、感謝の気持ちをしっかりと伝えるためにも、今年のお歳暮は「贈り方」から見直してみませんか?