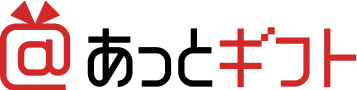ソーシャルギフトとは?SNSマーケティングに役立つ使い方や注意点を解説

公開日: 2025年10月08日
デジタルギフトの利便性の高さは、さまざまなプラットフォームで使用できる点にあります。なかでも今、SNSなどを通して贈るデジタルギフトは、「ソーシャルギフト」と呼ばれ、企業と顧客の関係構築の新たな手法としてここ数年注目されています。個人情報も不要で気軽に贈ることのできる「ソーシャルギフト」は、販促やファンづくりにも最適です。
この記事では、ソーシャルギフトの基本から活用方法、おすすめサービスまで詳しく解説していきます。
目次
ソーシャルギフトを活用した新しいマーケティング施策をお考えのご担当者様へ
「キャンペーンの応募率が伸びない」「SNSでの話題化が思うように進まない」――そんな課題を感じている企業様に、今注目されているのが“ソーシャルギフト”です。SNSやメールを通じて、住所や氏名などの個人情報を取得せずにギフトを届けられるこの仕組みは、顧客との接点をより気軽かつ効果的に創出できる新しい手法として、多くの企業で導入が進んでいます。
本記事では、ソーシャルギフトの基本から、企業が活用するメリット、具体的な活用シーン、注意点までを網羅的に解説。さらに、法人向けに特化したソーシャルギフトサービス「あっとギフト」の特徴もご紹介しています。
- SNSキャンペーンやフォロワー獲得施策
- 顧客満足度向上やロイヤリティ強化
- オンラインイベントの参加特典
- サンプリングやトライアル商品の代替
- 社員表彰や福利厚生
など、幅広いシーンで活用できるソーシャルギフトは、今後のマーケティング施策において欠かせないツールとなる可能性を秘めています。キャンペーンの成果を高めたい、顧客体験を向上させたいとお考えの方は、ぜひこの機会にソーシャルギフトの活用をご検討ください。
ソーシャルギフトの一つである「あっとギフト」の資料は以下よりダウンロード可能です。
資料ダウンロードソーシャルギフトとは
SNSやメール、メッセージアプリなどのソーシャルメディアは、現代の社会において、確固たる存在感をもつインフラとなっています。相手の住所や本名を知らなくてもコミュニケーションができるという、ソーシャルメディアの特徴を生かして生まれたのが「ソーシャルギフト」というスタイルです。
住所や電話番号、名前などの個人情報がわからなくても、ソーシャルメディア上で送りたい相手にプレゼント受け取り用のURLなどを送信し、受け取った相手はそのURLからデジタルギフトを受け取ることが可能。これによって、大量かつ多様なステークホルダーに向けてギフトを贈ることができるので、企業側にとってもメリットの多いギフト施策と言えます。
ソーシャルギフトの例
- 人気カフェチェーンやコンビニで使えるドリンクチケットやデジタルクーポン
- Amazonギフトカード
- もらった人が自由に選べるカタログ型のeギフト
- LINEの友だち登録キャンペーンでギフト配布
- Xで「その場で当たるくじ(インスタントウィン)」形式で当選者に配布
- Instagram投稿キャンペーンの参加者にギフト送付
- 誕生日のDMにeギフトを添付して送付
- クレーム対応後にコンビニギフトを送る
- 会員ランクアップ時に特別ギフト提供
- オンライン展示会の事前登録特典
- アンケート回答後にギフト提供
- 商談後のサンキューギフト
- 店舗で使える無料引換券をSNSで配布
- コンビニで使えるギフト券を送ることで新商品の購入促進
- 新規取引先への初回ご挨拶ギフト
- パートナー企業への感謝のメッセージにギフトを添える
- 資料請求後のステップメールにギフトを添付
- 月間MVPや営業成績優秀者、永年勤続表彰者への褒賞
- 社内イベントの景品
- 社員の結婚や出産などへのお祝い
- ギフト送付時に「〇〇日まで有効」と明記する
- リマインド通知やSNS投稿で再アナウンスする
- 使用期限の長いギフトを選ぶ
- ギフト利用手順を丁寧に説明する(図解付きなど)
- Q&Aやチャットボットなどで問い合わせ対応を補完
- スマホに不慣れな層にも配慮し、紙面やPDFマニュアルも用意
- 事前にキャンペーン利用規約を明示し、違反時の措置も明記
- 複数アカウントでの重複応募を防ぐシステムの導入
- 高額ギフトは抽選制または条件付きで提供
ソーシャルギフトが注目されるようになった背景
近年、企業のマーケティング施策としてソーシャルギフトの導入が急速に進んでいます。その背景には、いくつかの社会的・技術的な変化が絡んでいます。この章では、ソーシャルギフトが注目される理由について解説します。
SNSの普及と消費者行動の変化
総務省の「情報通信に関する現状報告の概要」によれば、SNSの利用率は上昇傾向にあり、これからも増えていくと予測されています。2022年には約1億人だったソーシャルメディア利用者数は、2027年には約1.13億人まで増加すると考えられています。この背景から、企業も広告やキャンペーンのプラットフォームとしてSNSを主戦場とするようになり「SNSで完結できるギフト施策」=「ソーシャルギフト」が注目されるようになりました。
コロナ禍以降の非接触文化の醸成とEC化の加速
もう一つ、ソーシャルギフトの需要が高まった理由に、新型コロナウイルスの影響があります。直接会うことができないという社会状況のなか、「対面を避けつつ心を伝える方法」としてソーシャルギフトという選択肢が急浮上するようになったのです。また、ここ数年のECやキャッシュレス文化の浸透もこの流れにさらに拍車をかけ、ギフトのデジタル化が一気に進行しました。
企業がソーシャルギフトを活用するメリットとは?
企業がソーシャルギフトを活用すると、どのようなことが期待できるでしょうか? 一般的には、ソーシャルメディアを利用する人の多さやエンゲージメント率の高さによって、マーケティング施策の効率化や成果最大化を期待して導入する企業が多いようですが、ソーシャルギフトを企業が活用するメリットはそれだけではありません。そこで、企業がソーシャルギフトを導入することで得られるさまざまなメリットをみていきましょう。
個人情報にまつわる取得・管理の負担が削減できる
プレゼントキャンペーンは、マーケティング施策のもっとも一般的なもののひとつとして長い間多くの企業が実施しています。けれども、従来のプレゼントキャンペーンでは、商品を発送するために氏名や住所、電話番号などの個人情報を取得・管理する必要がありました。しかし、消費者・ユーザーにおける個人情報への意識・不安の高まりから、その様なプライバシー性の高い情報を登録することへの抵抗感が高まっていて、取得が難しくなってきています。取得する企業側としても、個人情報保護の観点からその運用には細心の注意が求められ、結果的に運用負荷やセキュリティリスクが高くなるのが難点でした。
一方、ソーシャルギフトでは受け取り用のURLをSNSやメールで送るだけで完結するため、ユーザーの抵抗感が強い個人情報を取得せずにギフトを届けることが可能です。
簡単・低コスト&スピーディーに施策が展開ができる
これまで、ギフト施策を実施する上では、単に景品・プレゼント商品を調達するだけではなくて、その在庫管理や配送手配などにも、様々な手間や時間・コストがかかっていました。それに対して、ソーシャルギフトならこれらの物理的な作業が不要なため、施策の企画から実行までオンライン上でスピーディーに進めることができます。
たとえば「その場で当たる」SNSキャンペーンや、アンケート回答後の即時インセンティブ配布など、タイムリーな顧客接点づくりを手間ひまかけずに行うことも可能となるのです。また、配送・郵送が不要になるので、その分の費用や人件費も削減が可能になります。
相手の好みに合わせた柔軟なギフト選択ができる
個人の嗜好が多種多様になり、全員を満足させるギフトを用意することは至難の業です。こうした課題にもソーシャルギフトは有効で、受け取った人が自由に選んだり使ったりできる選べるタイプのギフトもあり、多種多様なギフトの中からターゲットのニーズに合わせて設定できることも魅力です。
たとえば、豊富なラインナップの中から受け取り手が好きなものを選べるカタログタイプのギフトや、街中やオンラインでの買い物に利用できる電子マネーやポイントなどは、汎用性の高いインセンティブといえるでしょう。
キャンペーン設計や顧客分析にも強みを発揮
企業のギフト施策にはその効果測定までを設計することが必須です。この点でも、ソーシャルギフトはデジタルツールとの連携性が高く、効果測定の面でも優れています。SNSを通じてソーシャルギフトを配布する専用のキャンペーンシステムと連携した場合は、配布数だけではなく、選択されたソーシャルギフトなどのデータが可視化できるため、次回以降の施策改善にも活用しやすいのが特徴です。
ソーシャルギフトの活用シーン

では、実際に現在、多くの企業ではどのようなソーシャルギフトを活用しているのでしょうか?活用されている主なシーンを6つのカテゴリに分けてご紹介します。
SNSキャンペーン・フォロワー獲得施策
代表的な活用例が、X(旧Twitter)やInstagram、LINEなどでのSNSキャンペーンです。「フォロー&リポストで抽選」「アンケートに答えるとその場でギフトが当たる」といった形式で、ソーシャルギフトをインセンティブとして活用します。キャンペーンによる拡散やUGC(ユーザー生成コンテンツ)創出により、ブランディング強化や認知拡大に効果的です。以下のような活用例があります。
顧客満足度向上・ロイヤリティ強化
既存顧客との関係性を深めるために、誕生日や契約記念日などのタイミングでソーシャルギフトを贈るという活用法もあり、実際に取り入れている企業も増えています。また、カスタマーサポート対応の一環として、トラブル時の補償やお詫びとしてギフトを提供することも効果的です。顧客体験の改善手段としても高く評価されています。以下のような活用例があります。
オンラインイベントやセミナーの参加特典
オンラインセミナーは新規顧客の獲得や、事業理解促進などに有効なタッチポイントとして現在多くの企業で実施しています。せっかくの機会ですから、参加者との距離を縮めたり、より高い関心をもってもらったりする施策を用意したいものですが、こうした場合にも参加者にお礼としてソーシャルギフトを提供するケースも増えています。さらに、こうしたインセンティブを用意することで、参加率やアンケート回答率を高められることにもつながります。住所収集が不要なため、利用しやすいのも魅力です。以下のような活用例があります。
サンプリングやトライアル商品の代替手段
新規顧客獲得や、リピーター増加のための施策として従来の店頭試供品や紙のクーポンに代わり、デジタルギフトを使ったプロダクト体験の提供も可能です。ギフトと引き換えに商品を購入・体験してもらうことで、定着率やリピート率の向上が期待できます。以下のような活用例があります。
取引先やパートナーへのお礼に
取引先や外部パートナーへのちょっとしたお礼や挨拶代わりにも最適です。たとえば、商談後や資料請求のフォローアップとして、さりげなく感謝を伝えるツールとしても活用できます。以下のような活用例があります。
社員表彰や福利厚生として
最近では、社員への表彰や感謝の気持ちを示すギフトとして活用されるケースも増えています。テレワークの普及により従業員との直接的な接点が減った中でも、ソーシャルギフトは簡単に気持ちを伝えられる手段として評価されています。以下のような活用例があります。
ソーシャルギフトを活用する際の注意点
その手軽さゆえに「落とし穴」に気づかないまま運用を始めてしまうと、ユーザー体験の低下やトラブルにつながることもあるので注意が必要です。
ギフトの使用期限に注意
もっとも気をつけなければいけないのが、使用期限の取り扱いです。ソーシャルギフトの多くは、受取期限や引換期限が設定されています。期限がわかりにくかったり期間が短かったりすると、受け取り手が気づかずに期限切れとなることもあり満足度の低下につながることもあるので、気をつけたいところです。以下のような対策が考えられます。
利用方法がわかりにくいと満足度が下がる
ギフトの受け取り方や利用方法がわかりにくく、ギフトが活用されずに終わってしまう、という残念な事態になってしまうことも少なくありません。ソーシャルギフトを準備する際は、受け取り手が理解しやすいように、受け取り方から使い方まで、わかりやすさを意識して送るように心がけたいものです。以下のような対策が考えられます。
想定外の利用や転売への対策
デジタルギフトは匿名性が高いため、転売やなりすましなどの悪用リスクにもつながります。企業のブランドイメージに直結するため、利用規約の整備や配布対象の明確化が欠かせません。以下のような対策が考えられます。
対策
ソーシャルギフトサービスなら「あっとギフト」がおすすめ
ソーシャルギフト市場は年々拡大を続けており、それに伴い多様なサービスが登場しています。企業がマーケティングや販促活動に取り入れる際には、サービスの特徴や強みを理解し、自社に最適なプラットフォームを選ぶことが重要です。
「あっとギフト」は法人向けソーシャルギフトに特化したプラットフォームです。ギフト券や電子マネーなど、汎用性の高い商品が豊富なので、幅広いニーズに応えることが可能です。また、デジタルギフトの提供はもちろん、キャンペーンツールの提供やカスタマー対応まであらゆる業務をワンストップでサポート・丸投げ可能なため、ビジネス用途での導入が増えています。
まとめ
企業のマーケティング施策において、SNSとの親和性が高く、個人情報を最小限に抑えながらユーザー満足度も高められるソーシャルギフトは、今後のデジタルプロモーションにおける「標準ツール」となる可能性を秘めています。
ただし、ターゲットのニーズにあわせたギフトを用意し、目的に合わせた施策になるように設計・運用することが重要です。自社のマーケティング戦略にソーシャルギフトをどのように組み込むかお悩みの場合は、一度ソーシャルギフトサービスに相談してみるのもいいでしょう。