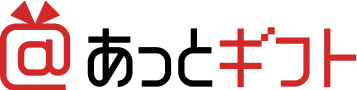モニター調査とは?調査の種類や進め方、謝礼の相場や工夫を徹底解説!

公開日: 2025年10月01日
新商品やサービスを出しても「本当に売れるのか」「消費者に響くのか」不安に感じたことはありませんか。担当者にとって、消費者の本音をつかむことはヒットを左右する大きなカギとなります。そのため、「モニター調査」は、普段見えにくい消費者のリアルな声を聞く上で有効な手段です。そこで、この記事では、モニター調査の基本から効率的な進め方、そして調査の質を高めるための工夫までを幅広く解説します。
目次
キャンペーン施策の改善をお考えのご担当者様へ
「キャンペーンを実施しても応募が伸びない」「SNSでの話題化につながらない」といった課題を感じている方は少なくありません。実はその原因、賞品や特典の選び方だけでなく、キャンペーン全体の体験設計にある可能性があります。ターゲットの嗜好や季節感、SNS映え、費用対効果など、複数の視点から賞品を設計することで、応募率や拡散力を大きく高めることができます。
本記事では、キャンペーン賞品の役割や選定のポイント、ターゲット別のおすすめ景品、そして実際の成功事例までをわかりやすく紹介しています。キャンペーンの成果を最大化するには、「何を贈るか」だけでなく、「どう届けるか」「どう喜ばれるか」にまで目を向けることが重要です。
こうしたキャンペーン施策と非常に相性が良いのが、法人向けデジタルギフトサービス「あっとギフト」です。「あっとギフト」では、豊富なデジタルギフトを柔軟かつスピーディに提供できるだけでなく、オリジナルデザインの演出やキャンペーン運営の代行までワンストップで対応可能です。初期費用なし・後払い対応など、導入のしやすさも魅力のひとつです。
資料ダウンロードモニター調査とは
この記事をご覧になっているマーケティング担当者の中には、新しい製品やサービスを世に出す前に「実際に使った人はどう感じるのか?」を知ることができ、その声を商品に反映することができたら、もっと良いものを提供することが出来るのでは、と思う方もいるのではないでしょうか。それを実現する手段の一つが、本稿で取り上げる「モニター調査」です。
モニター調査とは、特定の対象者に商品やサービスを体験してもらい、その感想や意見をアンケートやインタビューで収集して分析するリサーチ方法のことを指します。対象者を年齢や職業、住所、年収など所定の条件で絞り込み、一定の期間を設けて目的に応じて継続的に回答・データを取得します。
ホームユーステストのように日常生活の中で商品を試す方法もあれば、会場に集まってもらい複数人でグループインタビューを行うケースもあり、調査の方法もいくつかあります。調査の目的は、消費者の本音を集めて製品・サービスの改良や販促に役立てること。企業にとっては、単なるアンケート以上に「消費者視点」を収集できることが特徴であり、メリットであります。
モニター調査の手法・種類
先述のとおり「モニター調査」と一口にいっても対象者へのアプローチ方法や収集するデータの深さによって、具体的な調査方法が幾つかあります。ここでは代表的なモニター調査の手法を5つご紹介します。

Web調査
最も手軽に実施できるのがWeb調査です。Webアンケートを用いて対象者から回答を収集する方法で、比較的低コスト・短期間で多くのデータを収集できるメリットがあります。匿名性が高いことからモニターも気軽に回答しやすく、集計も自動化・効率化されていることが多いため、商品テストやサービスの第一印象をクイックにリサーチしたい時に有効です。
ただし、インターネットに不慣れな層から回答を得にくく、その調査形態から、回答内容の質の確保が問題になる場合もあります。
郵送調査
アンケート用紙やサンプルを郵送し、対象者に回答を返送してもらう方法です。インターネット利用の不得手な層や、利用環境がない層にもアプローチできるのが強みです。Webと比べて丁寧に回答してもらえるとされています。
一方で、Webや対面・会場調査と異なり回答記入の方法を制約・管理しにくいため、回答内容に不備が生じやすく、また、回収・集計までに時間や手間がかかること、回収率が低くなる傾向にある点には注意が必要です。
ホームユーステスト/サンプル調査
実際に商品サンプルを対象者の自宅に送付し、一定期間使用してもらったうえで感想をアンケートで収集する方法です。日常生活に近い環境での使用感を聞けるため、消費者の「リアル」と本音を引き出せるのが大きなメリットと言えます。食品や化粧品、日用品の調査でよく活用されています。
しかし、通常の郵送調査などと比べて、製品の配布・発送などで相対的にコストがかかりがちです。回答者の使用方法にもバラつきが生じるため、回答回収後の分析力が問われます。
グループインタビュー
対象者を会場に集め、モデレーターが質問を投げかけながら参加者に自由に意見を交換してもらう形式です。リアルタイムに生の「声」を拾うことができ、参加者の対話の中で新しい気づきが生まれるのが特徴で、製品コンセプトや広告表現を検証したい場面に向いています。
ただし、モデレーターの力量によって回答の質が大きく左右されることや、グループの構成によっては少数派の意見や本音を引き出しにくくなる恐れもあります。
デプスインタビュー
一対一で深く掘り下げるインタビュー手法です。ほかの調査にありがちな、表面的な回答の中では見つけられない動機や心理を明らかにできるため、高価格帯の商品や専門性の高いサービスのリサーチに適しています。
その反面、グループインタビューとは異なり一対一である分、所要時間やコストが高くなりがちであることと、主観に偏りがちのため分析のスキルが求められます。
モニター調査のメリット・デメリット
新商品やサービスの開発にあたり、「消費者のリアルな声をどれだけ正確に集められるか」が大きなカギとなります。モニター調査はその手段として非常に有効ですが、実施するにあたってはメリットとデメリットの両方を知っておくことが大切です。
モニター調査におけるメリット
モニター調査の最大のメリットは、製品を実際に使った意見が生の声を得られることで、単なるアンケートでは得られない消費者の本音と具体性のある消費者の情報を収集できる点です。ホームユーステストなど調査方法によっては、より生活の中でのリアルな評価を得ることもできます。使用感や改善点を具体的に知ることができ、商品開発や広告・マーケティング戦略の大きなインサイトにもなり得ます。
継続的なモニター調査を行う場合は追跡調査や比較調査ができるので、例えば、使い始めと3か月後の比較などといった分析を行うことも可能です。
モニター調査におけるデメリット
一方で、モニター調査には注意すべき点もあります。
まず、モニター属性に偏りが生じる可能性です。一般的に、調査に積極的な層に偏りがちで、市場全体を代表しにくいことがあります。また、調査に慣れたモニターは「模範的な回答」や「企業が望む回答」をしがちで、一般消費者とは異なる行動・意識を持っている場合もあります。
加えて、単純なアンケートやインタビューと比べて、コストや手間が掛かりがちです。モニターへのサンプルの手配や発送にかかる費用・手間のほか、継続的に調査を行う場合はその管理も負担としてのしかかります。
モニター調査の流れ
モニター調査を成功させるには、ただ調査票を配布するだけでは不十分です。企画段階から集計・分析まで、一連の流れをしっかり検討・準備することが重要です。ここでは、一般的なモニター調査のステップを整理して解説します。
1. 調査の企画
まずは調査の目的を明確にします。「新商品の使用感を知りたい」「広告表現の理解度を確認したい」など、企業の課題に合わせてテーマを設定します。
この段階で、仮説仮設を立てたり、どのような対象者からどのような情報を収集するのかを大まかに決めたりしておくと、その後の調査・質問の設計がスムーズになります。
2. 調査方法の選定
企画で決めた目的に応じて、調査方法を選びます。予算や期間、体制(外部委託含む)などを考慮する必要があります。
- Webアンケートで多数の回答を低コスト・効率的に収集
- 郵送調査でネット環境のない層も対象に調査
- ホームユーステスト/サンプル調査で日常生活に近い使用感を取得
- 会場インタビューやグループインタビューで消費者の声を深掘り
調査・質問の形式や内容によって得られる回答の量や質が大きく変わってきます。メリット・デメリットも踏まえて「どのようなデータや情報を得たいか」から逆算して調査方法を選定するといいでしょう。
3. 調査の設計
次に、実施計画を具体化します。対象者のスクリーニング、質問設計、実施スケジュールを含めた調査設計です。調査方法に応じて、たとえばWebアンケートであれば、どのツール・外部サービスを利用するか、インタビューであれば会場や当日のスタッフのロジ・手配も必要です。
ここで重要なのが謝礼の設定です。適切な謝礼は回答率や回答の質を高める効果があります。所要時間や回答者の負担の度合いに合わせて、現金やデジタルギフト、記念品などをお礼として用意することで、参加者のモチベーションが向上します。
4. 調査実施・実査
計画に沿って、実際に調査票を作成し、対象者や製品、調査方法ごとの必要な環境・ツールの手配を行い、アンケートやサンプルを配布します。
ホームユーステストでは実際に商品を使用してもらい、一定期間後に回答を回収します。会場でのインタビューやグループディスカッションの場合は、モデレーターが進行役となり、参加者の率直な意見を引き出します。期間を要する調査もありますので、進行状況の確認もするようにします。
5. 集計・分析
回答を集計し、分析します。データに不備がないかチェックを行います。
定量データは集計処理を行い、定性データは自由記述やインタビュー内容を分類・整理してインテリジェンスを抽出し、詳細に分析を進めていきます。この段階で、調査目的に沿った改善ポイントや戦略上の示唆を明確にすることが重要です。
モニター調査のコツ・ポイント
モニター調査を計画通りに進めていたとしても、期待していたほど有効なデータが得られないことがあります。その原因の多くは、調査の細かい設計や運用の中にあります。どんなに最適な方法や優れた手法を選んでいても、対象者がミスマッチであったり、質問が分かりにくかったり、謝礼の設定が不適切だったりすると、回答率や回答の質に影響します。
データの質や活用度を高めるには、調査設計の段階でいくつかのポイントを押さえておくことが必要です。この章では、モニター調査をより効果的に行うための具体的なコツやポイントを整理します。
スクリーニングで対象者を適切に選ぶ
まず、調査の目的に合った対象者を正しく選ぶことが大切です。たとえば、サンプル調査やホームユーステストでは、実際に商品を購入・利用する可能性のある層を選ぶことで、より実務に活かせる意見を得られます。
スクリーニングの方法としては、年齢、性別、ライフスタイル、過去の購入経験などを条件にアンケートで絞り込むケースが一般的です。適切な対象者を選ぶことで、データの信頼性が格段に向上します。
設問設計は分かりやすく、答えやすく
回答率や回答の質を高めるためには、分かりやすく、答えやすい設問設計が非常に重要です。質問が曖昧だったり複雑すぎたりすると、回答者は混乱し、回答の質が下がります。設問を作る際には以下の点に注意しましょう。
- 具体的で明確な質問:どの場面で、どのように使ったかなど詳しく問う
- 回答形式の工夫:選択式・評価スケール・自由記述を適材適所で使い分ける
- 一度に聞きすぎない:複数のテーマを1つの質問に詰め込まない
謝礼の工夫で回答率と質を向上
回答者に渡す謝礼は、モニター調査の回答率や回答の質に大きく影響を与えます。謝礼の内容を事前に周知しておくことで、参加者の意欲やモチベーションを高めることができます。
従来は自社製品のほか現金、紙やカードタイプの商品券・ギフトカードを贈るケースが主流でしたが、手配や管理のコストとリスクの問題もありました。そこで、最近では贈る側にとっても受け取る側にとっても便利な「デジタルギフト」を活用する企業も増加しています。
モニター調査の謝礼の相場
モニター調査を実施する際、謝礼をどのように設定するかは回答率やデータの質に直結します。謝礼額は高すぎても低すぎてもいけず、参加者のモチベーションを維持できる内容にすることが不可欠です。調査の種類や対象者に応じた適切な謝礼額を設定するようにしましょう。ここでは、一般的なモニター調査における謝礼の相場感を整理します。
参考:アスマーク社FAQ アンケート協力者への謝礼の相場はどのくらいですか?
Webや郵送での調査の場合
Webや郵送でのアンケートは多くの回答を集められる手法ですが、謝礼を設定することでその回答率は大きく向上します。一般的には、1回あたり数百円〜1,000円程度が目安です。簡単な質問や短時間で回答できるアンケートであれば数百円、内容が詳細で所要時間が長い場合は1,000円前後が妥当とされています。
ホームユーステスト/サンプル調査の場合
サンプル調査やホームユーステストは、対象者に商品を使ってもらう必要があるため、Webアンケートよりも謝礼がやや高めに設定される場合もあります。1,000~5,000円程度が一般的ですが、商品の使用期間や調査の手間によって変動します。
インタビュー・グループインタビューの場合
会場で実施するグループインタビューやデプスインタビューでは、参加者が一定時間拘束されるため、謝礼は5,000円〜10,000円程度が相場です。謝礼の設定が適切でないと、参加者の集まりが悪くなるだけでなく、回答の質にも影響することがあります。
モニター調査の謝礼にはあっとギフトがおすすめ
モニター調査では、回答率やデータの質を高めるために謝礼の工夫が必須です。従来は現金や郵送での商品提供が中心でしたが、近年は手軽に渡せて利便性も高いデジタルギフトを活用する企業が増えています。 そこでおすすめなのが、法人向けのアンケート&デジタルギフトサービスを展開している「あっとギフト」です。
魅力的なデジタルギフトの謝礼で回答率向上
あっとギフトでは、ギフトカードや電子マネー、コンビニでの商品の引換券、人気飲食店で使えるギフトなど、幅広いジャンルのデジタルギフトをご用意しています。
汎用性の高いギフトも多く、回答者が好きなギフトを選べる商品タイプもご提供可能ですので、年齢性別問わず、多くの方に喜んでいただけます。またギフトの金額もご要望に合わせて柔軟に設定することが可能です。発送作業や問い合わせ対応も、すべてあっとギフトにお任せください。
Webでも会場でも謝礼を渡しやすくて管理がラク
あっとギフトでは、デジタルギフトをURL形式で納品することが可能です。謝礼のデジタルギフトを回答者にメールやSMSでURLを送るだけで完了させられますので、紙タイプの商品券を郵送することにより生じる手間や送料負担がありません。受け取った回答者もURLをクリックするだけで、デジタルギフトの取得が可能。さらに、メールやSMSの配信も、あっとギフトに丸ごとご依頼いただけます。
会場調査の場合は、あっとギフトでは便利な専用システム・ツールをご用意しています。調査スタッフが、謝礼のデジタルギフトを回答者に渡すために、スマホやタブレット端末などにQRコードを表示して回答者に読み取ってもらうだけでデジタルギフトを渡すことが可能。これなら、紙のギフトカードを渡して受領証を書いてもらう煩雑な手間を削減できますし、後日わざわざ個別にメールを送るような業務も発生しませんので、謝礼を渡す作業や管理がとても楽になります。
アンケートフォームを安心・簡単に活用できる
あっとギフトは、ギフトを送れるだけではありません。アンケートフォーム機能も備えているため、モニター調査のためのアンケート作成からお礼メール&謝礼の送付までワンストップでサポート可能です。
またセキュアなアンケートフォームですので、個人情報を取り扱うモニター調査においても安心してお使いいただけます。
あっとギフトは、管理コストを抑えながら質の高いモニター調査を行うための実用的なソリューションをご提供しています。
モニター調査を成功させるために
モニター調査は、企画段階から設問設計、対象者選定、謝礼の設定まで、丁寧に設計することが成功の鍵です。さらに、スクリーニングや設問設計、謝礼の工夫を行うことで、回答率やデータの質を高められます。
この記事でご紹介したポイントを押さえていただくことで、企業側は単なるデータを集めるだけでなく、消費者のリアルで意味のあるインテリジェンスを活かした商品開発やマーケティング戦略の立案も行えます。モニター調査を有効活用し、より質の高いマーケティング活動を実現しましょう。