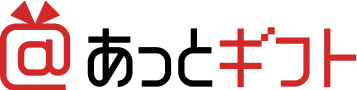【挨拶状の文例付き】 取引先・顧客へ贈るお中元マナーと最新ギフト事情

公開日: 2025年10月14日
ビジネスシーンにおける「お中元」は単なる贈り物ではなく、相手との信頼関係を形にする大切な儀礼です。時期や品物の選び方、挨拶状の書き方ひとつで、取引先や顧客への印象が大きく変わってくるため、マナーを押さえた対応が欠かせません。また、近年では経費削減や業務効率化の観点から、定番のカタログギフトに代えてデジタルギフトを検討する企業も増えています。本記事では、お中元の基本マナーやおすすめギフトについてご紹介します。
お中元のマナーと最新ギフト事情
「お中元を贈りたいが、何を選べばよいか迷っている」「形式的な贈り物になってしまい、相手に本当に喜ばれているか不安」――そんな悩みを抱えるご担当者様も多いのではないでしょうか。 ビジネスにおけるお中元は、単なる季節の贈り物ではなく、取引先や顧客との信頼関係を築く重要なコミュニケーション手段です。
近年では、従来の食品やカタログギフトに加え、住所不要・選べる・業務効率化を実現する「デジタルギフト」が注目されています。中でも法人向けデジタルギフトサービス「あっとギフト」は、ギフトの選定から配布、挨拶状の演出、送付履歴の管理までを一括で対応でき、総務・秘書業務の負担軽減と相手満足度の向上を両立できる新しい選択肢です。
本記事では、お中元の基本マナーから最新のギフト事情、そして「あっとギフト」を活用したスマートな贈り方まで、現代のビジネスシーンに即した情報をまとめています。 慣習を大切にしながらも、時代に合った贈り方をぜひご検討ください。
資料ダウンロードお中元とは?
お中元とは、日頃お世話になっている人へ感謝の気持ちを伝えるために、夏に贈り物を届ける習慣です。この風習の由来は中国の「三元」という行事のひとつ「中元」にあり、日本では祖先の霊を供養する風習と結びつき、江戸時代には目上の人やお世話になった人に贈り物をする文化として広まりました。今日ではビジネスでも重要な慣習のひとつとなり、夏の贈答文化として定着しています。
個人間そして企業間でも「お中元」は夏の伝統的な儀礼として今でも親しまれており、食品やお酒、スイーツやフルーツなど、季節を感じられる品物が多く選ばれています。サマーギフトや夏の贈り物とも呼ばれ、暑い時期に相手を気遣う「暑中見舞い」の意味合いを込めることもあります。
一方、お中元と並んでよく耳にするのが「お歳暮」です。どちらも感謝を伝える贈り物ですが、違いは贈る時期とニュアンスにあります。お中元は夏に贈り、上半期のお礼や暑中見舞いを兼ねる意味合いが強いのが特徴です。対してお歳暮は年末に贈り、一年の締めくくりとして「来年もよろしく」という意味を込めて贈るのが通例です。
ビジネスシーンにおけるお中元
ビジネスにおけるお中元は、取引先や顧客への感謝を示し、良好な関係を保つための大切な儀礼です。個人間の贈り物とは違い、法人同士のやりとりではマナーや時期、予算感に注意が必要です。
お中元を贈る時期
もっとも重要なのが「時期」です。一般的なお中元の時期は、関東では7月初旬から15日頃まで、関西では7月中旬から8月15日頃までが目安となるなど、地域差があります。そのため、先方の習慣に合わせて贈るのが好ましいでしょう。特に企業に贈る場合は、先方の夏季休業期間や繁忙期も考慮することも必要です。
| 地域 | 時期 |
|---|---|
| 北海道・北陸(一部)・東海・関西・中国・四国 | 7月15日~8月15日 |
| 東北・関東・北陸(一部) | 7月1日(7月初旬)~7月15日 |
| 九州 | 8月1日~8月15日 |
| 沖縄 | 旧暦7月13日~7月15日 |
最近では、配送が込み合う前に対応するなど、少し早めにお中元を贈るケースも増えています。もし贈るのが遅れてしまう場合、7月15日を過ぎた贈り物は「暑中見舞い」、立秋(8月上旬頃)を過ぎたら「残暑見舞い」として送るようにしましょう。
お中元の相場
法人間のお中元の相場は、3,000~5,000円程度が一般的です。ただ、取引規模や相手企業との関係性によっても予算感は変わってきます。特に重要顧客や大口取引先には、10,000円前後のやや高めの品物を選ぶケースもあります。
しかし近年は経費削減の流れもあり、高額品よりもコストパフォーマンスや受け取りやすさが重視されるようになっています。従来のお中元の定番を踏まえつつも、時代に合った方法を検討することが、今後ますます大切になりそうです。
ビジネスにおけるお中元のマナー
ビジネスでのお中元は、ただモノを贈れば良いというものではありません。のしや表書き、渡し方ひとつで相手に与える印象は大きく変わります。ここでは基本のマナーと、見落としやすいポイントを整理しておきましょう。
のし・表書き
お中元を贈る際は、包装の上に紅白蝶結びののし紙をかけるのが基本です。表書きは「御中元」とするのが一般的。ただし、贈る時期が7月15日を過ぎた場合は「暑中御伺」「暑中御見舞」などに変えます。さらに立秋(8月上旬頃)を過ぎる場合は「残暑御伺」「残暑御見舞」とするのがマナーです。
表書きの下段には贈り主の会社名を入れますが、個人名を併記するかどうかは相手との関係性によります。よりフォーマルにするなら「株式会社〇〇 営業部 田中太郎」といった書き方がおすすめです。
渡し方・贈り方
近年は働き方改革の影響もあり、訪問を控え、配送を利用する企業が増えています。ここでは、訪問して手渡しする場合と、配送で送る場合、それぞれのケースで気をつけるべき点についてまとめます。
訪問して手渡しする場合
- 訪問のタイミング
- 持参時のマナー
- 相手が不在の場合
お中元を直接持参する場合は、事前に「ご挨拶に伺いたい」と訪問日時をアポイントメントするのが基本です。繁忙期に急に訪れるのは失礼にあたるため、訪問の数日前には必ず連絡を入れましょう。
お中元は紙袋や風呂敷に包んで持参しますが、渡す際は品物を袋から出して両手で渡します。「つまらないものですが」ではなく、最近では「日頃の感謝の気持ちです」など前向きな言葉を添えるのが良いとされています。
不在で手渡しできないときは、持参したことを伝える名刺や挨拶状を受付や担当者に預けると丁寧です。
宅配・配送で贈る場合
- 贈る際の連絡
- 送り状の宛名
配送の場合でも、いきなり品物を送らず、事前に一報を入れるのが望ましいとされています。電話やメールで「本日お中元をお送りしました」と連絡することで、相手も受取対応や社内分配の準備ができます。
法人宛に贈る場合でも、記載する宛名は状況に応じて以下のように変えましょう。
| 手法 | 宛名例 |
|---|---|
| 会社全体宛 | 社長や代表者名で送るのが一般的 |
| 特定の担当者や部署宛 | 「株式会社〇〇 営業部御中」のように記載する |
| 個人宛 | 個人名をフルネームで書き、会社名は肩書きとして併記するのが丁寧 |
ビジネスの現場では「個人の私物化」を避けるため、法人宛てにするケースが増えています。ただし、長年の慣習や相手の意向によるため、初めて贈る際は先方に確認するのが安心です。
挨拶状と文例
お中元を贈る際は、品物に同封するか、別送で挨拶状を添えるのがビジネスマナーです。特に配送が主流の現代では、顔を合わせずに贈るケースが多いため、挨拶状は相手への心遣いを伝える重要な役割を果たします。
以下は、法人間で使えるシンプルな文例です。
株式会社〇〇
営業部 部長 佐藤花子様
拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
日頃の感謝のしるしとして、心ばかりの品をお届けいたしました。
ご笑納賜りますれば幸甚に存じます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
株式会社〇〇
営業部 田中太郎
お中元で避けた方がよいもの
ビジネスシーンでは以下のような品物は避けるのが無難です。
- 現金や高額すぎる商品券(不正取引などを疑われるリスクがあるため)
- 刃物類(縁を切ることを連想させるため)
- 高額すぎる贈り物(贈賄や便宜供与と誤解される恐れがあるため)
- 宗教色の強い品物
会社によっては受け取り自体を辞退する規定が定められている場合もあるため、事前に先方に確認を入れておくと安心です。
喪中や忌中の場合
相手先もしくは自身が喪中の場合でも、お中元は「お祝い」ではなく「感謝の贈り物」であるため、必ずしも控える必要はありません。ただし、忌中(四十九日まで)の期間中は避ける方が無難です。また贈る場合は華美な包装を避け、表書きは「御中元」のままで問題ありませんが、挨拶状に一言お悔やみの文を添えると丁寧です。
ビジネスでのお中元におすすめの品物は?
お中元の時期になると悩むのが「今年は何を贈るか」という問題です。定番を選ぶ安心感もありますが、取引先や顧客に喜んでもらうためには、相手の好みやトレンドを押さえておきたいところです。ここでは、法人向けお中元で人気の品物と、それぞれの特徴をご紹介します。

食品・菓子類
法人間のお中元では、いわゆる「消えもの」と呼ばれる食品や菓子類が根強い人気です。特に夏は以下のようなアイテムが好まれます。
- ゼリーや涼菓子
- 焼き菓子や詰め合わせ
- 高級調味料やグルメセット
涼しげで見た目にも華やか。大人数で分けやすく、冷蔵保存で日持ちする商品が多いため、取引先のオフィス向けにもぴったりです。
洋菓子の詰め合わせは季節を問わず人気です。個包装になっているものは社内で配りやすく喜ばれます。
取引先に少し特別感を出したいときに選ばれます。地域の名産品や限定商品を選ぶ企業も多いです。
飲料
夏場はやはり飲料系の贈り物が定番です。
- ビールセットなどのお酒類
- ジュース詰め合わせ
法人のお中元ランキング上位の常連ギフトです。ブランドや種類にバリエーションが多く、贈る側としても選びやすいのがメリットです。またビール以外にも、日本酒や焼酎、ワインなどを贈るケースもあります。
アルコールを贈りにくい取引先や健康志向の企業にはジュースが安心です。特に果汁100%の高級ジュースなど、少し特別感のある商品が人気です。
カタログギフト
ビジネスシーンにおけるお中元で定番化しているのがカタログギフトです。
- 相手が自由に品物を選べるため、好みを外す心配がない
- 金額感が一目で分かるので予算管理がしやすい
- 会社でまとめて手配しやすい
こうした理由から、特に取引先が多い企業や支店が多数ある企業には非常に便利です。
デジタルギフト
近年、注目されているのがデジタルギフトです。受け取り側が住所を開示しなくても、メールアドレスだけで簡単に受け取れるのが最大のメリットです。実際に「配送先の登録が面倒」「相手の異動で住所が不明」など、従来のギフトでは起こりがちなトラブルを避けることができます。
また最近では、ビールギフトやグルメカード、選べるデジタルカタログなど選択肢も増えており、カタログギフトからの切り替えを検討する企業も増えつつあります。食品、飲料、カタログギフトなど上述した商品は全て同様のデジタル媒体でのカタログギフトにすることも可能です。昨今はリモート勤務を取り入れている企業も増えていることもあり、配送トラブルを避け、かつビジネスマナーにも配慮できるデジタルギフトの評価が高まっています。
ビジネスでのお中元には「あっとギフト」
取引先や顧客へのお中元の手配は重要な業務ではあるものの、ギフトの選定から手配、挨拶状の作成や配送作業など準備は多岐にわたり、工数もかかってしまうことが多いです。そこで作業効率を上げつつ、相手の満足度向上にも役立つのがデジタルギフトを活用した支援サービス「あっとギフト」です。
ギフトの種類が豊富
あっとギフトは、法人向けのデジタルギフト提供サービスです。AmazonギフトカードやPayPayポイントなどの電子マネーやポイントに交換できるデジタルギフトだけではなく、お菓子や飲料、お取り寄せグルメなどにも交換できるグルメカードやデジタルカタログギフトなど、魅力的なギフトを豊富に取り揃えています。またサービスを利用する場合、各商品の発行元との交渉や個別契約は不要です。
選べるギフトで贈り先の選択肢が広がる
取引先によって好みや社内規定は様々です。あっとギフトが提供する選べるタイプのデジタルギフトなら、贈り先に好きな商品を選んでもらうことができるため、無駄もなく、満足度も高まります。また、相手の好みを気にする心配も不要になり、贈る側の負担軽減にもなります。
マナーも大切に。台紙やメッセージカード対応
ビジネスギフトでは、贈り物の中身だけでなくマナーも重要です。あっとギフトでは、オリジナルの台紙やメッセージカードをつけることができるため、無味乾燥な贈り物にならず、きちんとした印象を演出することができます。法人向けに特化したサービスなので、堅実な企業文化を持つ取引先にも安心して利用できる点が魅力です。
送付実績も管理できる
複数の取引先にお中元を贈る場合、「誰に、いつ、何を送ったか」 の管理は非常に重要です。あっとギフトでは、贈り先の送付状況をデータで一元管理できるため、贈るに際してのトラブルを防ぐこともできます。来年以降の計画策定にも役立ちます。
お中元の段取りを丸投げでき、総務・秘書の負担を軽減
従来のギフト手配では、商品の選定、のしや包装の手配、配送先リストの作成など、多くの作業が負担になりがちでした。あっとギフトなら、一括でデジタルギフトの手配から配布用サイトの作成、メール配信まで対応できるため、忙しい担当者にとって大きな助けとなります。
まとめ
お中元は単なる贈り物ではなく、ビジネスにおいて大切な「信頼と感謝のコミュニケーション」です。取引先や顧客との関係をより良好に保つためにも、贈る時期やマナーをきちんと押さえたうえで、相手に喜んでもらえる品を選びたいものです。
近年は、従来の食品やカタログギフトに加え、デジタルギフトという新しい選択肢も登場しています。社内の業務負担を減らしつつ、相手のニーズに柔軟に対応できるあっとギフトのデジタルギフトサービスは、ぜひ一度検討してほしい手段です。慣習を大切にしながらも、時代に合った形で贈り物のコミュニケーションを進化させること。それがお中元を通じた、これからの賢いビジネスの在り方と言えるのではないでしょうか。