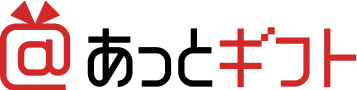顧客満足度調査の基本と活用法 CS調査の指標と実施・改善ポイント

公開日: 2025年10月01日
「お客様は本当に満足しているのか」――担当者であれば一度は気になったことがあるのではないでしょうか。そこで役立つのが、顧客満足度調査・CS調査です。最近ではCX調査(顧客体験調査)も行われています。NPS®(ネットプロモータースコア:顧客ロイヤルティを図る)、CSI(顧客満足度指数)などの様々な指標を検討したうえで行うケースも多く、こうした調査はデータに基づいて課題を発見し、具体的な改善策を立てることができます。本記事では、そのための指標や調査方法、設計のポイント、実務で使える活用法をわかりやすく解説します。
目次
キャンペーン施策の改善をお考えのご担当者様へ
「キャンペーンを実施しても応募が伸びない」「SNSでの話題化につながらない」――そんな課題を感じているご担当者様は少なくありません。
その原因は、単に賞品の魅力だけでなく、顧客体験(CX)全体の設計や満足度の把握が不十分であることにあるかもしれません。
今、企業が注目すべきなのは、顧客満足度調査(CS調査)やCX調査を活用したキャンペーン施策の改善です。
満足度や体験の質を数値化し、データに基づいて改善を行うことで、応募率や拡散力、そしてブランドロイヤルティの向上につなげることができます。
こうした調査・改善サイクルと非常に相性が良いのが、「あっとギフト」です。
「あっとギフト」の調査での活用方法
- アンケートフォームの作成代行布
- 回答後すぐにデジタルギフトを配布
- オリジナルデザインの演出(ブランドイメージに合わせたギフト画面のカスタマイズ)
キャンペーンは、単なる販促施策ではなく、顧客との信頼関係を築く重要な接点です。満足度調査を通じて得られた「気づき」をもとに、体験価値を高めることで、応募率の向上、SNSでの話題化、リピーターの増加、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。
「あっとギフト」を活用すれば、調査・改善・ギフト提供までを一貫して効率化でき、より多くの顧客の声を集め、施策に反映することが可能です。キャンペーン施策の成果を高めたいとお考えの方は、ぜひこの機会に、顧客満足度調査とデジタルギフトの融合による新しいアプローチをご検討ください。
顧客満足度調査とは
企業が継続的に成長していくためには、顧客の声を正しく把握することが欠かせません。その中心的な手段が「顧客満足度調査」です。
顧客満足度調査は、企業が提供する商品やサービスに対して、顧客がどれだけ満足しているかを定量・定性的に把握するための施策です。単なる「満足していますか?」という質問だけでなく、実際の利用体験や不満点までを幅広く収集することで、企業は自社の強みや改善点を具体的に理解できるのがメリットと言えるでしょう。
この調査の目的は、顧客の声をデータとして蓄積し、商品・サービスの改善やリピート率向上、競合との比較分析、さらにブランドや商品・サービスの信頼性向上に活かすこと。設問の作り方や調査方法次第で、顧客体験の詳細な分析や、将来的なLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の予測にもつなげることができます。
顧客満足度調査の目的
顧客満足度調査を行う最大の目的は、顧客の声を正しく把握し、企業の成長やサービス向上に活かすことです。単なる「満足しているか」の数値だけでなく、具体的な課題や改善点を見つけることで、経営戦略や現場の施策に直接つなげられます。ここでは、主な目的を4つに分けて解説します。
商品・サービス改善
調査で集めた回答から、どの機能やサービスが顧客に評価されているか、どこに不満があるかを把握できます。たとえば、ECサイトの購入手続きで「操作がわかりにくい」という声が多ければ、UI改善や手順の簡略化を検討できます。こうした改善は、満足度の向上だけでなく、離脱防止にも直結します。
競合他社との比較
顧客満足度調査では、同じ市場の競合と比べて自社の強みや弱みを明確にすることも可能です。「サービス対応は自社の方が速いが、価格や商品ラインナップでは負けている」といった具体的な比較結果は、競争戦略や差別化ポイントの検討に役立ちます。
リピーター・LTVの向上
顧客満足度が高いと、再購入率やLTVが向上します。例えば、アンケートで「このサービスを友人に勧めたい」と回答した顧客には、ロイヤルティを高める特典やフォロー施策を展開できます。満足度と行動意向を結びつけることで、売上の安定化や長期的な収益増加につなげることができます。
商品・サービスの信頼性向上
調査結果は、顧客に「この企業は自分の声を聞いてくれる」と感じてもらう材料にもなります。例えば、顧客の意見を反映して新サービスを改善・提供すれば、口コミやSNSで良い評判が広がることもあり得ます。信頼性の高い企業イメージを築くことは、長期的なブランド価値の向上にもつながります。
顧客満足度調査の主な指標
顧客満足度調査において、「どの指標に基づいて実施すれば自社にとって本当に役立つのか」と迷うことも少なくありません。単純に満足度だけを測るだけでは、改善すべきポイントが見えにくいからです。NPS®やCSAT、CESなど、それぞれの指標には特徴や活用法があります。ここでは、実務で使いやすく、改善や分析につなげやすい代表的な指標をわかりやすく解説していきます。
NPS®(Net Promoter Score/ネットプロモータースコア)
NPS®(ネット・プロモーター・スコア)は、CX(顧客体験)全体を評価し、ロイヤルティを測るための重要な指標です。
「この商品やサービスを友人や同僚に勧めたいと思いますか?」という質問で測っていきます。
回答は0~10点で評価され、
9~10点:推奨者(満足度が高く積極的に勧めたい人)
7~8点:中立者(どちらでもない人)
0~6点:批判者(不満があり勧めない人)
に分類し、スコア化します。
例えば、オンラインショップの調査で「配送が速い」と答えた人は推奨者になりやすく、「サポートに不満がある」と答えた人は批判者に分類されます。これにより、どの体験が推奨につながり、どこが不満の原因かを把握できます。
NPS®は単なる「満足度」ではなく、リピート購入や口コミによる紹介など、実際の行動意向に直結する指標です。改善に取り組む際は、「批判者の不満を減らす」「中立的な顧客を推奨者に変える」ことを意識すると効果的です。
注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。
CSI/ACSI(Customer Satisfaction Index/American Customer Satisfaction Index:カスタマー・サティスファクション・ インデックス/アメリカン・カスタマー・サティスファクション・インデックス)
CSIやACSIは、アメリカを中心に世界30か国以上で活用されている顧客満足度を総合的に数値化する指標です。「顧客期待値」「知覚品質」「知覚値」「顧客不満度」「顧客忠実度」の5つの項目に関する複数の設問を組み合わせて質問し、その回答結果の平均値から算出します。単なる「満足していますか?」という問いだけでなく、製品・サービスへの信頼や愛着、品質や価格に対する評価、購入前の期待と購入後の感想のギャップなどを総合的に分析できるのが特徴です。
例えば、家電メーカーの調査では、「商品の機能や性能」「購入手続きのわかりやすさ」「アフターサポートの対応」など複数の質問を設け、顧客の回答を集計してCSIやACSIスコアを算出します。このスコアを定期的に追うことで、自社サービスの改善効果や市場での位置づけを把握でき、競合他社との比較も可能です。
CSIやACSIは、顧客満足度の変化を時系列で追いやすく、具体的な改善施策の優先順位を決める際にも役立ちます。また、スコアの算出方法が標準化されているため、業界ベンチマークとしての活用もしやすく、経営層への報告資料としても信頼性の高いデータになります。
注:ACSIおよびそのロゴは、American Customer Satisfaction Index LLCの登録商標です。
JCSI(日本版顧客満足度指数)
JCSIは、上述のCSIをベースに日本の企業やサービス向けに開発された顧客満足度指標で、国内市場の特性を反映しています。サービス産業生産性協議会(SPRING)がサービス産業約30業種を対象に毎年調査を行い公表をしています。
CSIの5項目に相当する「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「顧客満足」「ロイヤルティ」に加えて、顧客が友人や家族に薦めたいかの「推奨意向度」を加えた6つの項目を総合的にスコア化することで、業界や競合との多角的な比較も可能です。
具体的には、たとえば通信会社や家電メーカーのJCSI調査では、「契約手続きのわかりやすさ」「サポート対応のスピード」「製品の品質や耐久性」といった設問を用いて、顧客体験の各ポイントを評価します。
また、日本の消費者は品質や信頼性に敏感で、きめ細かなサービスを重視する傾向があります。JCSIはこうした国民性を指標設計に取り入れているため、海外の調査指標とは異なる独自の分析が可能です。
このデータをもとに、企業は改善すべき接点や施策の優先順位を明確化できます。国内市場に特化しているため、日本の消費者行動や期待に沿った分析ができ、競合ベンチマークとしても活用しやすいのが特徴です。
CSAT(Customer Satisfaction Score:カスタマー・サティスファクション・スコア)
CSATは、特定の商品やサービスに対する「満足度」をシンプルに測る指標です。通常は「非常に満足」「満足」「やや不満」「不満」などの選択肢で評価し、特定の体験や接点ごとに顧客の満足度を把握できます。
例えば、オンラインショッピングでのCSAT調査では、「注文から配送までのスピード」「梱包の状態」「問い合わせ対応のスムーズさ」といった具体的な接点ごとにアンケートを取ります。この結果から、どの部分で顧客が満足しているか、どこに改善が必要かを明確に把握でき、施策の優先順位をつけやすくなります。
CSAT調査は簡易で実施しやすく、特定サービスの改善効果を短期間で確認できる点が特徴です。特に接客やサポート対応、購入体験の改善など、日々の業務改善に直結する指標として活用されます。
CES(Customer Effort Score:カスタマー・エフォート・スコア)
CESは、顧客が目的を達成する際にどれだけ手間や労力を感じたかを測る指標です。「問題解決にどれだけ手間がかかったか」「問い合わせ対応はスムーズだったか」といった設問を使い、顧客体験の負荷を数値化します。
例えば、コールセンター対応のCES調査では、「問い合わせから解決までにかかった時間は適切でしたか?」「担当者の対応はわかりやすかったですか?」といった質問で評価を集めます。CESスコアが高い場合は、顧客がスムーズに体験を完了できていることを意味し、逆にスコアが低い場合は改善が必要な接点が明確になります。
CESは、顧客満足度だけでは見えにくい「手間やストレス」の部分を把握できるため、CX改善に直結する指標です。特にサポート対応や手続きの簡略化など、顧客の負荷を減らす施策を優先的に検討する際に役立ちます。
顧客満足度調査の流れ
顧客満足度調査は、単にアンケートを実施するだけでは十分な成果が得られません。調査目的の明確化から結果の活用まで、計画的なステップを踏むことが重要です。ここでは、実務で使える具体的な流れを解説します。

1. 調査の目的と仮説を決める
目的によって設問や分析方法が変わってきます。まずは、「商品改善のため」「競合比較のため」「リピーター率向上のため」など、調査の目的を明確にするところから始めましょう。また、目的を決めると同時に仮説を立てておくと、調査結果から優先的に改善すべきポイントを導きやすくなります。
2. 調査対象者を決める
調査対象者は、目的に応じて適切に選定することが重要です。全顧客対象の場合もあれば、特定の商品利用者や最近サービスを利用した顧客など、ターゲットを絞ることで分析の精度が高まります。
3. 調査時期・タイミングを決める
調査のタイミングも結果に影響します。商品購入直後やサポート対応後など、顧客の体験が鮮明なタイミングでアンケートを送ると、より正確なデータを収集することができます。また、季節やキャンペーン期間などの外部要因も考慮することが重要です。
4. 調査方法・ツールを選定する
調査方法には、オンラインアンケート、電話調査、対面ヒアリングなどがあります。近年は、専門のアンケートツールや外部サービスを活用する企業も増えています。専門サービスを活用すれば、効率的に実施・集計することが可能になります。ツール選びでは、分析機能や回答率向上の仕組みがあるかなど、サポート機能が充実しているものを選ぶといいでしょう。
5. 調査票を設計
設問設計は、データの質を左右する重要なステップです。回答者が答えやすく、分析に活かせる内容にすることが大切です。また、アンケートの謝礼を用意すると回答率が向上します。最近は、オンライン上でのアンケートが増えていることもあり、オンラインで手軽に送れるデジタルギフトを活用した謝礼が人気です。
6. 実施・回収
アンケートを配布したら、回答状況を確認しながら回収を進めます。リマインドメールやフォローアップを適切に行うことで、回収率を高めることができます。
7. 集計・分析・改善
回収したデータを集計・分析し、目的に沿ったインサイトを抽出します。指標を組み合わせることで、改善の優先順位を明確化できます。分析結果は、商品改善や顧客体験向上の施策に具体的に反映させることが重要です。
顧客満足度調査のポイント・注意点
顧客満足度調査を行ったとしても、設問が不適切だったり、実施タイミングがずれていたりすると、改善につながるインサイトをうまく引き出すことはできません。効果的に調査を行うためには、押さえておきたいポイントや注意点がいくつか存在します。ここでは、それらのポイントについて、具体的な例を交えながら解説します。
設問はシンプルに、回答しやすく
設問が長すぎたり、選択肢が多すぎたりすると、回答率が下がるだけでなく、データの質も低下します。例えば、サポート窓口の満足度を聞く場合は、「対応は迅速でしたか?」「対応はわかりやすかったですか?」といった具体的な質問に絞ると、改善ポイントが明確になります。
回答者の負担を減らす
アンケートは短時間で答えられるように設計しましょう。5分以上かかる場合、途中で離脱する顧客が増える傾向にあります。できる限り短時間で回答できるように設問数や回答方法を調整することも必要です。また最初に「このアンケートは○分で終わります」など目安時間を明記しておくのもいいでしょう。さらに、回答意欲を高めるために、デジタルギフトなどの謝礼を用意すると回収率が大幅に向上します。
データ分析は目的に沿って行う
集めた顧客満足度データは、目的に沿った形で分析することが重要です。単に平均スコアを見るだけでは、不満の原因や改善点を見落としてしまいます。
例えば、NPS®調査で「批判者(Detractor)が多い」場合、その顧客層がどの製品・サービスで不満を感じているのかをセグメント別に分析すると、改善の優先順位が明確になります。また、CSATやCESの結果を組み合わせて見ることで、「満足度は高いが手間がかかる」といった、顧客体験の課題も把握可能です。
さらに、時間軸での推移を追うことで、施策が効果を出しているかどうかも確認できます。分析は目的に沿って深掘りするほど、実務で活かせる具体的な改善策につながります。
結果は必ず改善に活かす
顧客満足度調査のデータは、集めただけでは意味がありません。最も重要なのは、分析結果を具体的な改善策に結びつけることです。例えば、アンケートで「配送の遅れ」に不満を感じる顧客が多ければ、物流フローの見直しや配送業者の変更といった施策を検討します。また、サポート対応への不満が目立つ場合は、担当者教育やFAQの充実など、改善策を即座に打ち出すことが可能です。
改善策を実施したら、再度アンケートで効果を測定するサイクルを回すことも重要です。これにより、施策の成果を数値で確認でき、継続的な顧客体験(CX)の向上につながります。調査は「実施すること」よりも、「改善に活かすこと」が真の目的だと意識しましょう。
顧客満足度調査にはあっとギフトがおすすめ
顧客満足度調査を実施する際、回答率を高め、正確なデータを確保・分析することは大きな課題です。しかし、これらすべての工程を自社で行うためには人手も時間も必要となります。効率的に調査を行うためには、アンケートの企画・実施・回収から謝礼のデジタルギフトの提供まで、顧客満足度調査に必要な機能を相談できる「あっとギフト」がおすすめです。
「あっとギフト」とは?
デジタルギフトを活用した販促・キャンペーン施策をサポートする法人向けサービスです。アンケートフォームの作成からデジタルギフトの配布までワンストップでご利用できる仕組みをご提供しています。
従来は、アンケートを集計して後日デジタルギフトを配布したり、アンケートフォームを自身で作成したりと準備や運用に手間も時間もかかる施策でした。あっとギフトではご希望のアンケート内容を伝えてもらうだけで、複雑なフォーム作成などシステム設定は一切不要でデジタルギフトを付与するアンケートを実現できます。
手間なく簡単にアンケート作成
回答してほしいアンケート内容をワードやエクセルで作成頂くだけでアンケートフォームを「あっとギフト」で作成することが可能です。自身でシステムの設定を行って、アンケートフォームを作成するなど複雑な対応は一切不要です。
デジタルギフト配布の作業工数を大幅削減
「あっとギフト」ではアンケート回答後すぐにデジタルギフトの付与をするという機能も対応しています。回答後その場でギフトを配布することで、回答率の向上に寄与するケースも。ギフトの種類においても、AmazonギフトカードやPayPayポイントなどの代表的なギフトからコンビニ商品の引換券まで、ユーザーのニーズに合わせたギフトを豊富に取り揃えています。
顧客の声を未来の価値に変える顧客満足度調査
顧客満足度調査は、単にアンケートを実施するだけではなく、目的に沿った設計・適切な分析・改善への活用があってこそ価値を発揮します。そのためにも、「あっとギフト」のようなサポートサービスを活用しながら、効率的に多くの顧客の声を集めるのがいいでしょう。
顧客満足度調査は、改善のための「気づき」を得る手段であり、顧客との信頼関係を築く重要なステップです。本記事で紹介したポイントや注意点を押さえつつ、定期的に調査と改善を繰り返すことで、商品やサービスの質を向上させ、リピーターの増加やLTVの向上にもつなげることができます。