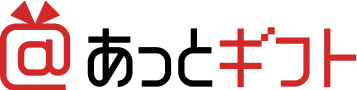ブランド調査で失敗しない方法 設計から分析までの実務ガイド

公開日: 2025年10月08日 更新日: 2025年10月10日
「ブランド調査をしたけれど、結局どう活かせばいいのかわからない」――そんな経験はありませんか。単に知名度を測るだけでは、消費者の心をつかむことはできません。ブランド調査は、顧客が抱くイメージや競合とのポジショニング、広告・プロモーションの効果検証までを多角的に分析できる重要な手法です。本記事では、ブランド調査の基本から具体的な手法、成功のポイントまでを実務に役立つ視点で解説します。
ブランド調査を成果につなげたい企業担当者様へ
「ブランド調査をしても、戦略にどう活かせばいいのか分からない」「広告やキャンペーンの効果が曖昧で、次の施策に反映しづらい」――そんな課題を感じている方も多いのではないでしょうか。今、企業が注目すべきは、ブランド調査を通じて顧客の認識・感情・行動を多角的に把握し、ブランド価値を高める戦略的アプローチです。認知度やイメージ、ロイヤルティ、広告効果などを定量・定性・行動データの3つの視点から分析することで、施策の精度と成果を大きく向上させることが可能になります。
そして、こうした調査を「実施しやすく」「成果につなげやすく」するための強力なパートナーが、B2B向けデジタルギフトサービス「あっとギフト」です
- アンケートフォームの作成から謝礼ギフトの配布までをワンストップで提供
- 電子マネーや飲食店ギフトなど、豊富な選べるギフトで回答率を向上
- ブランドイメージに合わせたギフト画面のカスタマイズも可能
- セキュリティ対策済みで、個人情報を扱う調査にも安心
「あっとギフト」を活用すれば、ブランド調査の設計・実施・分析・改善までを効率化でき、より多くの顧客の声を集めて戦略に活かすことが可能です。 本記事では、ブランド調査の基本から手法、成功のポイントまでを実務に役立つ視点で解説。ブランドの「今」を正しく知り、「これから」に活かすためのヒントをお届けします。
資料ダウンロードブランド調査とは
ブランド調査とは、自社ブランドが消費者にどのように認知され、どんなイメージを持たれているかを多角的に把握・分析する調査です。単に「知っている人の割合=認知度」だけを見るものではなく、ブランドに対する顧客の評価や感情、競合との違い、さらには購買やロイヤルティにどう結びついているのかまでを明らかにすることを目指します。
他のマーケティング調査と比べると、ブランド調査はより「長期的なブランド価値」を測る視点が強いのが特徴です。たとえば広告調査は特定のキャンペーン効果を検証するものですが、ブランド調査では「広告がブランドイメージにどのような影響を与えたのか」まで分析します。また顧客満足度調査がサービスや商品単位の満足度を測るのに対し、ブランド調査は企業やブランド全体の印象を評価する点が大きな違いです。顧客満足度調査に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
顧客満足度調査の基本と活用法 CS調査の指標と実施・改善ポイント キャンペーン施策の成果が伸び悩んでいる方へ。応募率や話題化につながらない原因は、顧客体験の設計にあるかもしれません。本記事では、顧客満足度調査(CS調査)やCX指標について解説。NPS®やCSATなどの指標をもとに、体験価値を高める方法や、「あっとギフト」を活用した効率的な施策運用まで、実務に役立つ情報を網羅します。
ブランド調査は、マーケティングやブランディングの戦略を立てるうえでの出発点となる重要な調査です。競合との差を明確にし、ブランドを強くしていくために欠かせない役割を持っています。
ブランド調査の目的と必要性
ブランド調査を行う最大の理由は、ブランドが消費者にどのように受け止められているかを正確に把握することにあります。消費者の心理やブランドイメージ、競合とのポジショニングを多角的に分析し、マーケティングやブランディング戦略の土台をつくることが最大の目的です。ここでは、ブランド調査が企業にとって不可欠である理由を、5つの観点から詳しく解説します。
認知度とポジショニングの把握
ブランド調査の出発点は、消費者が自社ブランドをどの程度知っているか、そして市場でどのような立ち位置にあるかを把握することです。例えば、競合ブランドとの比較で「認知度は高いが、特徴が伝わっていない」といった課題が見つかることがあります。この情報は、新しいプロモーション戦略や広告メッセージの設計に直結します。
さらに、自社ブランドが特定のターゲット層で過小評価されている場合や、競合に誤認されやすい場合にも、調査結果をもとに戦略的なポジショニング調整が可能になります。
ブランドイメージの評価
ブランドイメージの評価は、消費者がそのブランドにどのような印象や感情を抱いているかを把握するために行います。単に「良い」「悪い」といった感覚だけでなく、ブランドが持つ特徴や強み・弱みを具体的に分析することが重要です。「信頼できる」「高級感がある」「親しみやすい」といった感情的な側面も含まれます。化粧品ブランドの場合なら、「肌に優しい」「自然派」「高級感がある」といった特徴がどの程度消費者に伝わっているかを調査するイメージです。 ブランド調査を通じて、消費者が自社のブランドに対して抱く具体的なイメージを把握することができ、自社の弱点や改善点、強みが明確になっていきます。
ブランドロイヤルティの測定
ブランドロイヤルティは、顧客がそのブランドを選び続けるかどうか、その愛着の度合いを示すものです。リピート購入などの継続意向や、知人や友人に薦めたいかどうかの推奨意向などを調査することで、顧客がブランドに対してどれだけ愛着や信頼を持っているかが分かります。たとえばコーヒーチェーンの場合、定期的に利用しているか、他店よりも優先して選ぶか、友人にすすめるかなどを調査することで、ロイヤルティの高さを多角的に評価することができます。
ブランドエクイティの把握
ブランドエクイティとは、消費者がそのブランドに対して感じる「価値」「信頼」「好意」などが積み重なり、企業にとって大きな力となる状態を指します。これは単なる売上や認知度だけではなく、「このブランドだから選びたい」と思ってもらえる長期的な強み、つまりブランド力そのものを意味します。
ブランドエクイティが高ければ、他社よりも価格を高く設定しても受け入れられやすくなるなど、価格競争に巻き込まれることなく利益を上げることができます。こうした情報は、マーケティング施策だけでなく、経営判断や投資判断にも役立つため、ブランド戦略を考える上で非常に重要です。
広告・プロモーション効果の検証
広告やプロモーションを行った際に、その施策がブランド価値にどの程度影響を与えたかを検証することもブランド調査の目的に含まれます。単発のクリック数や売上だけでなく、「消費者のブランド認知度」「イメージ」「購入意向」に与えた変化を測定します。これにより、広告投資の費用対効果を長期的な視点で評価でき、次の施策に反映させることができます。また、複数の施策を比較することで、ブランド強化に最も効果的なアプローチを特定することも可能になります。
ブランド調査の手法
ブランド調査では、消費者がブランドをどう認知し、どのような評価をしているのかを多角的に把握するため、複数の調査手法を組み合わせて実施することが一般的です。ここでは代表的な3つの手法をご紹介します。
| 手法 | 特徴 | 具体例 | 活用ポイント |
|---|---|---|---|
| 定量調査(Quantitative Research) | 大規模サンプルから統計的に分析可能。認知度やイメージを数値化できる | Webアンケート、郵送アンケート、街頭・会場調査、ブランドリフト調査 | 誰にどのくらい知られているか、ブランドの浸透度や施策効果の定量評価に有効 |
| 定性調査 (Qualitative Research) | 少人数を対象に、深い心理や価値観を把握。数値では捉えきれない消費者の意識を分析 | デプスインタビュー、フォーカスグループインタビュー、投影法 | ブランドイメージの背景や消費者の潜在ニーズを理解。広告・メッセージ改善に活用 |
| 行動データ調査 (Behavioral Data Analysis) | 実際の行動や購買データ、Web/SNS活動を分析。態度と行動の両面を把握 | 購買データ分析、Web/SNS分析、口コミ分析 | 実際の購買傾向や行動パターンを把握。広告・施策効果検証、顧客セグメント分析に有効 |
定量調査(Quantitative Research)
定量調査は、大規模なサンプルから統計的に分析可能なデータを取得する手法です。ブランド認知度、イメージ評価、購入意向などを数値化できるため、意思決定の根拠として活用しやすいのが特徴です。
- Webアンケート
- 郵送アンケート
- 街頭・会場調査
- ブランドリフト調査
顧客や潜在顧客にメールやSNSでアンケートを配信。ブランドの認知度やイメージ評価を素早く把握できます。この方法は、新製品発売前後の認知度の変化を測定する場合などに適しています。
属性を管理したターゲット層にアンケートを送付する方法です。回答率はWebに比べやや低いものの、正確性が高く、年齢層や地域を絞った分析に向いています。
イベントや商業施設で調査を実施します。特定地域の消費者動向や来場者のリアルな印象を把握可能です。
広告やキャンペーンの前後で、認知度・イメージ・購入意向の変化を測定する方法です。どの施策がブランド価値にプラスになったかを定量的に評価できます。
定量調査は、「誰にどのくらい知られているか」「どのイメージが強く浸透しているか」を可視化する上で欠かせません。競合ブランドとの比較や時系列でのトレンド分析にも有効です。
定性調査(Qualitative Research)
定性調査は、少人数を対象に消費者の深い心理や価値観を探る手法です。ブランドの印象や好感度、態度の背景にある理由を明らかにすることで、単なる数値だけでは見えない洞察を得られます。
- デプスインタビュー(深層面接)
- フォーカスグループインタビュー
- 投影法
個別インタビューで、ブランドに対する感情や購入行動の理由を深掘りしていきます。たとえば「なぜ競合ブランドより自社製品を選ぶのか」ということを明確化できます。
複数人で意見交換を行い、共通認識や潜在的なブランド価値を抽出する方法です。異なる視点からの意見を同時に把握できるため、新規ブランドやキャンペーンアイデアの検証に有効です。
消費者が自分の意識を直接表現しにくい場合に、写真や物語、擬人化した質問を用いて間接的に心理を引き出します。潜在的なブランドイメージや態度を可視化でき、広告メッセージの改善にも役立ちます。
定性調査は、ブランドの強みや弱み、消費者の期待とのギャップを把握する際に特に有効です。定量調査では捉えきれないニュアンスや心理的要因を明らかにできる点が大きな強みです。
行動データ調査(Behavioral Data Analysis)
行動データ調査は、消費者の実際の行動や購買データ、WebやSNS上の活動を分析する手法です。意識や回答だけでなく、実際の行動に基づく分析ができるため、ブランド戦略の精度向上に直結します。
- 購買データ分析
- Web/SNS分析
POSデータやECサイトの購入履歴を分析し、ブランド選好やリピート傾向を把握する方法です。たとえば、新キャンペーン実施後にどの層のリピート率が向上したかなどを明らかにできます。
検索履歴、SNS投稿、口コミ、レビューなどからブランドへの言及量や評価を分析する方法です。ブランドイメージの変化や競合との差別化ポイントを把握できます。たとえば、SNSでのポジティブ投稿増加は、広告施策の影響を示す指標となります。
行動データ調査は、顧客が実際に何を選んでいるか、どのような行動をしているかを客観的に把握できる点が最大のメリットです。特に広告やキャンペーンの効果検証、顧客セグメント分析、新規施策のPDCAに活用できます。
ブランド調査成功のコツ
ブランド調査では、ただアンケートを取るだけでは十分な成果は得られません。調査の目的を明確にし、対象者や手法を適切に設計することが、正確で活用しやすいデータを得るためのポイントです。成功するブランド調査では、調査設計から回答者への配慮まで、一つひとつのステップを丁寧に行うことが重要です。この章では、調査結果を戦略に直結させるための具体的なポイントを紹介します。
1. 調査目的と評価指標を明確にする
まず、何を知りたいのか、調査の目的をはっきりさせることが重要です。
- ブランド認知度を把握したいのか
- ブランドイメージの改善点を知りたいのか
- 広告やキャンペーンの効果を測定したいのか
目的によって、調査手法や質問項目、分析方法が変わってきます。KPIや評価指標をあらかじめ設定しておくことで、調査結果を戦略に直結させやすくなります。
2. 調査対象の設定とサンプル設計を適切に行う
「誰に聞くか」「何人に聞くか」「どのような属性比率で聞くか」をしっかり計画することで、調査結果を偏りなく信頼できるデータに導くことができます。
- 調査対象の設定(誰に)
- サンプル数の設計(何人に)
- 属性分布の調整(属性比率に)
調査対象は、ブランドの評価やイメージを把握したい人に絞る必要があります。たとえば、新しい化粧品ブランドを展開する場合、既存顧客だけでなく、競合ブランドを利用している20〜40代女性も対象にすることで、ブランドの市場での立ち位置を正確に把握できるようになります。
サンプルとは、調査のために選定した対象のことです。人数が少なすぎると信頼性が劣るものの、多すぎてもコストが上がるだけです。アンケート調査では「400サンプル」が目安とされていますが、目的や予算、クロス集計など分析の想定に合わせて最適なサンプル数を検討しましょう。
特定の層に偏った結果にならないように、性別・年齢・地域・購買行動などの属性比率を調整する必要があります。たとえば、全国20〜60代の男女を対象とする場合、各年代・性別の人数比率を母集団に合わせて調整します。
3. 適切な調査手法の選定と組み合わせ
ブランド調査では、定量調査・定性調査・行動データ調査の3つを組み合わせるとより効果的です。
- 定量調査で認知度やイメージを数値化
- 定性調査で背景にある心理や価値観を深掘り
- 行動データ調査で実際の購買行動やWeb/SNSでの反応を分析
手法を組み合わせることで、数字だけでは見えない洞察や戦略的示唆を得ることができます。
4. 質問設計と回答率向上の工夫
質問内容は、目的に沿った設計にすることが重要です。曖昧な質問や専門用語の多用は、正確なデータ取得を妨げます。また、回答率を高めるための工夫も必要です。
- アンケートの所要時間は短く設定し、事前に明記しておく
- 回答は選択式にするなど、回答者の負担を少なくする
- インセンティブを用意する
最近では、回答者へのお礼も込めて、手軽に贈れるデジタルギフトなどをインセンティブとして活用する企業も増えています。
5. 結果分析と施策への活用
ブランド調査では、分析結果をきちんと戦略に活かすことが1番大事です。得られたデータを整理し、以下のように活用します。
- 認知度やイメージの課題を改善施策に反映
- 自社ブランドのポジショニングの見直しや差別化ポイントの強化
- 広告やプロモーション効果の評価と次の施策へのフィードバック
分析結果をまとめただけで終わりにせず、具体的な施策に落とし込んで実行するところまでしっかり進めましょう。
ブランド調査にあっとギフトの活用を
ブランド調査を実施する際、回答率の確保や質の高いデータを集めることは大きな課題です。アンケートに協力してもらうための動機付けや、回答者にとってストレスの少ない回答環境を用意することが調査成功のカギとなります。そのようなときに役立つのが、法人向けに特化したアンケート&デジタルギフトサービスの「あっとギフト」です。
豊富な謝礼で回答率を向上
あっとギフトでは、電子マネー、コンビニ商品の引換券、人気飲食店で使えるデジタルギフトなど、幅広いギフトをご用意しています。汎用性が高いギフトも多く、対象者の回答モチベーションを高めることができます。ギフトの金額も柔軟に設定でき、在庫管理の必要もなし。また受け渡しはオンラインで完結するため、担当者にとっても運用がしやすく、回答者にとっても受け取りやすい仕組みとなっています。
簡単で安全なアンケートフォームを活用できる
あっとギフトは、ギフトを送れるだけではありません。アンケートフォーム機能もご提供しているため、ブランド調査のためのアンケート調査票作成からお礼メール&謝礼の送付まで、ワンストップでご利用いただけます。
回答してほしい内容をワードやエクセルで作成いただくだけで、「あっとギフト」のアンケートフォーム作成が可能です。ご自身でのシステム設定などは一切不要なので、作業工数を削減しながら調査アンケートを実施することが可能になります。またアンケートフォームはセキュリティ対策もされており、個人情報を取り扱うブランド調査においても安心してお使いいただけます。
ブランド戦略を強化するために
ブランド調査は、「知る」から「行動に活かす」までのプロセスがあってこそ価値が高まります。調査で得られたインサイトを具体的な施策に反映させることで、ブランドの強みをより鮮明にし、自社のブランドを魅力的な存在へと育てることができるのです。
「知る」だけで終わらせず、得られたデータを次の戦略に活かすことがブランドの成長につながります。まずは一歩、調査設計から始めてみましょう。