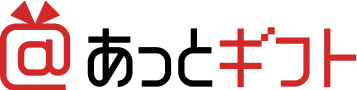デジタルギフトを購入する方法は前払い 後払い? 支払い方法や納品方法は?

公開日: 2023年12月20日 更新日: 2025年07月07日
目次
ギフト券など、キャンペーンで送る景品を購入する際、支払い方法や納品方法に迷う担当者の方も多いのではないでしょうか。
「ギフト券の前払いだと在庫管理が必要だし、納期に遅れるかも・・・」
「後払いは与信審査が心配・・・。使った分だけ請求のギフトってないのかな」
「どんな納品方法があるかよくわからない。」

そんな時は、在庫管理や発送が不要で、手間やコストを省けるデジタルギフトがおすすめです。
今回はデジタルギフトの支払い方法と、納品方法を徹底比較。それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
デジタルギフトは後払いできる?支払い方法を徹底比較。
デジタルギフトには3種類の支払い方法があります。
- 「前払い」
- 「デジポッド」
- 「後払い」
自社に合わせた方法で支払いができます。
それぞれの特徴を解説します。
デジタルギフトを「前払い」で購入する。
デジタルギフトを購入する前に、購入先に料金を支払います。その後、デジタルギフトが発行できるようになります。
メリットは?
購入する度の支払いが可能です。
デメリットは?
購入の度に請求処理が必要です。支払い日が決まっている企業では、納期が遅くなる場合があるので注意が必要です。
デジタルギフトを「デジポッド」で購入する。
デジポッドとは「一時的な預り金」のことで「保証金」を意味します。一定の金額を「前入金」しておき、デジタルギフトを発行すると、そのデポジットから料金が引かれていく仕組みです。デポジットの残高がなくなると、デジタルギフトの発行ができなくなります。
メリットは?
一定の金額を先に入金しておくので、購入の度に、入金する必要がありません。
デメリットは?
常に残高の管理をしておく必要があります。急にデジタルギフトが必要になった場合に、残高不足で購入できない、というトラブルも懸念されます。
デジタルギフトを「後払い」で購入する。
購入したデジタルギフトを「月末締め翌月末払い」といった、事後精算できる支払い方法です。
メリットは?
販売する企業が設定した与信枠内であれば、際限なく購入できます。事前の入金をしてから納品という流れではないので、前払いよりも短納期です。デポジットのように残高の管理も必要ありません。
デメリットは?
販売企業が与信枠を設定するケースが一般的ですが、企業規模によっては、与信枠が低かったり、設定されない可能性もあります。注意が必要です。
以上「前払い」「デジポッド」「後払い」の特徴をそれぞれ説明しました。
結果:デジタルギフトの支払いには「後払い」の利用がオススメです。
手元に現金がなくても購入でき、短納期も可能な「後払い」が最も便利です。
しかし、デジタルギフト事業者でも、与信枠の都合で後払いできない場合があるので、利用の前に確認が必須です。
デジタルギフトの納品方法を徹底比較。
デジタルギフトの納品方法は大きく分けて、3つあります。
- デジタルギフトのみを購入する。
- APIで連携する。
- デジタルギフト事業者が提供するキャンペーンシステムを利用する。
では、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
デジタルギフトだけを購入する。
CSVなど、デジタルギフト業者が指定した方法で納品します。デジタルギフトのみ必要な場合に利用できます。
メリットは?
自社でシステムを開発する必要がありません。メールにデジタルギフト事業者が発行した英数字やURLを記載するだけで利用できます。
デメリットは?
デジタルギフトの事業者によっては、最低発注数量や金額に関係なく手数料が発生し、小ロットでは利用しにくい場合もあります。
APIで連携する。
ポイント交換など、法人企業でエンドユーザーに表示する画面を所持している場合に利用できます。
メリットは?
エンドユーザーの要望で、その都度、APIでリクエストします。使用した分だけの精算ができます。
デメリットは?
システム開発が必要なため、導入した法人企業に負担がかかる場合があります。
キャンペーンシステムを利用する。
デジタルギフト事業者のTwitterやLINEを活用する方法です。インスタントウィン(即時抽選)や、応募サイトを構築します。後日、当選者を選定する「後日抽選」など、デジタルギフトを活用するキャンペーン一式をデジタルギフト事業者が請け負います。対応しているキャンペーンは、各デジタルギフト事業者によって異なります。
メリットは?
キャンペーンを一括でデジタルギフト事業者に委託できます。
デメリットは?
キャンペーンシステムも込みで利用料金が発生するため、当選者が少数だったりすると、割高になる可能性もあります。
以上、納品方法を比較しました。
顧客の用途に合わせて、納品方法を検討するのがベターです。
デジタルギフト事業者で提供しているサービスも異なるため、詳細は問い合わせて確認しましょう。
デジタルギフトは「あっとギフト」の利用がオススメ!
デジタルギフトは「あっとギフト」の利用がおすすめです。
「あっとギフト」なら「あっとギフト」自体が与信をとっているため、すべてのサービスで「後払い」が利用可能です。他社から購入して後払いできないものでも「あっとギフト」なら可能です。
納品方法も、デジタルギフトのみの購入、API連携、キャンペーンシステムの提供、すべてのサービスを利用できます。まずはご要望をヒアリングし、用途に合わせた適切なサービスをご案内します。
まずはぜひ、お問い合わせください。
「あっとギフト」で人気の商品ラインナップ
「あっとギフト」では人気の商品を取り揃えています。
PayPayポイント
誰でも簡単に利用できるのが特長です。コンビニエンスストアからスーパーマーケット、飲食店、ECサイトまで、幅広いジャンルの支払いに利用できる汎用性の高いデジタルギフトです。
Amazonギフトカード
大手通販サイトAmazon.co.jpでご利用いただけるデジタルギフトです。来店者促進キャンペーンで利用実績も多数あり、発行金額も1円から設定可能なので、少額の配布にも対応可能です。
セブン-イレブン デジタルギフト
全国21,400店舗以上(2023年2月末)のセブン-イレブンの商品と交換できるデジタルギフトです。豊富な商品と引き換え可能なため、予算に応じた商品引換券が発行できます。
サーティワン アイスクリーム
店頭で利用できる商品券です。利用者の好みのメニューに交換したり、テイクアウトの際に使用できます。好きなフレーバーのレギュラーシングルと交換できる「レギュラーシングルギフト券」もおすすめです。
まとめ
デジタルギフトの支払い方法と納品方法を解説しました。
支払い方法は「後払い」がおすすめです。
納品方法はそれぞれに異なったメリットとデメリットがあるので、自社の特徴に合わせて、検討してみるのがいいでしょう。