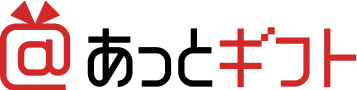企業発展に結びつく株主優待の導入メリット~優待品にはデジタルギフトがおすすめ~

公開日: 2025年04月17日 更新日: 2025年07月03日
個人投資家の7割以上が株式投資を行なう際、銘柄選びの基準にしている「株主優待制度」。株主に送る優待品が魅力的であるほど、株式を購入・長期保有してもらえる傾向があることから、多くの企業が導入しています。
そこで今回は、株主優待制度の基礎知識を解説するほか、おすすめ優待品も紹介します。
株主優待制度とは?
株主優待制度について
「株主優待制度」とは、企業が一定以上の株式を保有する株主に対して、デジタルギフトや商品券、自社製品・サービスを進呈する制度です。
日本経済新聞の報道によると、2024年、新たに株主優待制度を導入した上場企業は131社と前年より50社増え、累計導入社数も1530社と5年ぶりに増加。再び盛り上がりを見せています。
引用:日本経済新聞
- 2024年、新たに株主優待制度を導入した上場企業は131社と前年より50社増え、累計導入社数も1530社と5年ぶりに増加
株主優待制度を導入する目的
株式の保有数や保有期間に応じたインセンティブを得られることから、「株主の安定確保」がおもな導入目的です。
ほかにも、2018年から売買できる最低株式数が100株に統一され、個人でも株式を購入しやすくなったことから「個人投資家の獲得」、株主優待制度で「企業を知ってもらい、自社製品・サービスのファンになってもらう」という目的で、導入する企業も少なくありません。
引用:日本取引所グループ
- 2018年から売買できる最低株式数が100株に統一された
株主優待制度を導入するメリット・デメリット
メリット
株価の安定
長期投資家の獲得と維持につながるため、株価の安定化が期待できます。優待品の内容によって、株価へポジティブな影響をもたらす可能性もあります。
自社のファンが増える
株主優待制度をきっかけに企業の認知度やブランドイメージが向上します。優待品に自社製品・サービスを送ることで、愛用者増加にも寄与します。
企業と株主との関係強化
株主は、株主総会やセミナーなどに参加することができます。優待品の進呈に加え、これらの集いを通じて株主との関係性を強化できます。
デメリット
コストがかかる
優待品の購入費用、発送料、及びそれらにかかる人件費といったコストがかかります。
業務負担がかかる
日常業務に加え、株主総会や優待品の準備など、企業担当者の業務負担が増えます。
「あっとギフト」では、デジタルギフトの用意から配送まで一気通貫でサポート可能です。株主優待制度の導入にかかる業務負担を軽減するサービスをご用意しています。
詳しくは、お問い合わせください。
株価上昇だけじゃない!多様化する株主優待の恩恵
株主優待のある銘柄を選ぶ際、その指標として「総合利回り」があります。これは、株式の配当金と優待品の現金換算額を投資額で割ったもので、この値が高いほど、個人投資家にとってお得感があります。
そのため、優待品にデジタルギフトや商品券を採用し、高利回りとなる株主優待を発表後、3日連続で株価がストップ高になった企業も。
恩恵は株価上昇だけではありません。優待品に商品の割引カードを進呈したところ、顧客が増加し、全体的な売上の底上げに成功したケースもあります。
おすすめの優待品
デジタルギフト
優待品として株主に喜ばれるものは「日常使いができるもの」です。
「PayPayポイント」や「Amazonギフトカード」といったデジタルギフトは、全国のコンビニエンスストアやドラッグストア、オンラインショップなどで使用できるため、採用する企業が多いです。
また、注文・発送・管理がオンライン上で済ませられるため、コストや業務の負担軽減を図れるほか、デジタルギフトは少額設定ができるため、株式数や保有年数によって優待品を差異化することも可能です。
優待品にデジタルギフトが選ばれる理由については、以下の記事で詳しく解説していますので、そちらもご参考ください。
リアル商品券・リアルカード
デジタルギフト同様、全国どこでも利用できるため、株主に喜ばれるインセンティブです。
物理的な商品券が手元に届くため、安心感やお得感を醸成できるのが特徴です。また、商品券に感謝のメッセージを添えることで、企業からの気持ちもより伝わります。
自社製品・サービス
優待品に自社の製品やサービスを進呈することで、株主は企業のブランドに触れることができます。自社製品・サービスのPRにつながるほか、企業や製品・サービスのファンを増やす効果も期待できます。
カタログギフト
好きなものを選び、それが届くという二重の楽しさを提供できます。地域や季節ならではの産品・旬の食材を集めたカタログギフトもあるため、地域貢献、社会貢献にも寄与できます。
株主優待なら「あっとギフト」におまかせください!
担当者の業務負担を軽減!「あっとギフト」の株主優待の特長
デジタルギフトの調達
株主の属性に適したデジタルギフトの調達をお手伝いします。
台紙の手配
印刷会社と提携しているため、株主にデジタルギフトやリアル商品券を配布する際の専用台紙の一括手配が可能です。
オリジナルデザインの作成が可能
独自のデザインをほどこした専用カードを作成することで、PR強化、特別感の演出が可能。企業ブランドをしっかりアピールできます。
アンケート機能の追加が可能
株主が質問に回答してからデジタルギフトを受け取れるなど、アンケート機能を追加できます。自社や優待品に関する意見などを簡単に収集できます。
デジタルギフトとフィジカルカードから選択できるシステムの提供
株主によっては、優待品はフィジカルカード(紙やプラスチック製のカード)を希望する場合もあるので、デジタルギフトとフィジカルカードから選択できるシステムを提供します。
株主総会招集通知に優待品を同封して送付するための提案
株主総会招集通知と優待品の封入代行も含めた提案を行ないます。
株主専用コールセンターの運営
株主からの問い合わせなどに応対するコールセンターの運営を代行します。
企業に選ばれる!「あっとギフト」のその他の特長
デジタルギフトの種類が豊富
「あっとギフト」では、「PayPayポイント」や「Amazonギフトカード」など、多種多様なデジタルギフトを取り揃えています。若者の個人投資家が増えている昨今、株主のニーズに合った優待品を選択できます。
掛け払い制
法人向けデジタルギフト提供企業の中には前払いを採用しているところもありますが、「あっとギフト」は掛け払いが可能です。金券分だけ先に入金する必要がなく、まとめて支払えるので、精算業務を効率化できます。
初期費用・固定費ともに「0円」
「あっとギフト」は、初期費用・固定費用がかかりません。ランニングコストの軽減を図れる、0円から利用できるサービスもありますので、まずはお問い合わせください。
まとめ
新たに導入する企業が増加し、盛り上がりを見せている株主優待制度。「株主の安定確保」「個人投資家の獲得」「企業のファンづくり」を期待できますが、なかには優待品によって全体的な売上増に成功した企業もあるなど、さまざまな恩恵がもたらされています。
しかし、株主優待制度を導入することにより、株主総会の準備など企業担当者の業務負担増、優待品の手配などコスト負担増は避けられません。
そこで、「あっとギフト」の株主優待がおすすめです。
株主のニーズに合ったデジタルギフトの提案から株主専用コールセンターの運営まで、一気通貫でおまかせいただけます。
また、優待品にデジタルギフトを採用すれば、注文・発送・管理がオンライン上で完結できるので、コスト削減も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。